今回は関数の連続性に関する問題についてわかりやすく解説していきます。この分野は「連続性」や「右側極限/左側極限」といった小難しい用語や概念が登場してくるため、公式の意味や論証の進め方を理解するのが大変という特徴があります。
本記事では、用語の定義や公式の意味を解説しながら分かりにくい論証をなるべくかみ砕いて解説していきますので、是非最後まで一緒に確認していきましょう!
なお、入試問題などでは関数の連続性とセットで微分可能性もよく出てくるので、こちらは別の記事で解説しようと思います!
- 関数の連続性の調べ方を理解したい人
- 連続性を調べる際に出てくる用語の意味やイメージを感覚的に理解したい人
- 論証のコツを理解したい人
- 大学入試対策、定期テスト対策がしたい人
【問題&解説】関数の連続性に関する問題
【例題】関数の連続性の調べ方(難易度:★☆☆)
まずは基本問題を例に関数の連続性の調べ方を確認していきましょう。
関数 \begin{split} \small f(x)= \begin{cases} \small |x| \quad (x \neq 0)\\ \small \space 1 \quad \space \space (x=0)\\ \end{cases} \end{split} について、\(\small x=0\)における関数の連続性を調べよ。
☞ 一見複雑な関係式だが、端的に言うと\(\small x=a\)のちょっと右側やちょっと左側の\(\small y\)座標が\(\small f(a)\)と同じだったら連続ということ。
連続とは関数がつながっていること。関数がつながっているか否かは、特定の\(\small x\)の値の近傍で\(\small y\)座標の値が一致していることが確認できればよい。

特定の\(\small x\)座標の近傍での\(\small y\)座標が一致することを確認する方法として、特定の点(例えば \(\small x=a\)とする)のちょっと左側での\(\small y\)の値(左側極限)とちょっと右側での\(\small y\)の値(右側極限)を求めて、関数\(\small f(x)\)の\(\small y\)座標 \(\small f(a)\)と一致することを確認するのが一般的。

\(\small f(a)\)のちょっと右側や左側での\(\small y\)座標が全然別の値になっていたら、「おや?関数が途切れてるぞ!」と考えるわけだ。
このことを数式っぽくかくならば、『「左側極限値」 \(\small =\) 「\(\small x=a\)での\(\small y\)座標」 \(\small =\) 「右側極限値」』が成り立つということになるので、関数が連続になる条件のような関係式が成り立てばよいことになる。
「Point:関数が連続になる条件」より、\(\small x=0\)で関数\(\small f(x)\)が連続になる条件は、
\begin{split}
\small \color{green}{\lim_{x \to -0} f(x)} &\small \color{green}{=f(0)=\lim_{x \to +0} f(x)} \quad \cdots (*)\\
\end{split}
3つの値が等号で結ばれているのでそれぞれの値を求めていこう。
まずは一番簡単な\(\small f(0)\)から考えると、\(\small x=0\)のときの\(\small y\)の値なので問題の関数の定義から、\(\small f(0)=1\)…①.
次に \(\small \displaystyle \lim_{x \to -0} f(x)\)(左側極限)について考える。\(\small x \to -0\)は『\(\small x=0\)の左側からの極限』という意味なので、関数の\(\small x\)座標としては\(\small x<0\)の範囲と考えればよい。よって、\(\small x<0\)での関数 \(\small f(x)\)は
$$\small f(x)=|x|=-x$$
となることに注意。
以上より、
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to -0} f(x) = \lim_{x \to -0} -x=\color{green}{0 \space \cdots ②}\\
\end{split}
この時点で ①\(\small \neq \)② ⇔ \(\small \displaystyle \lim_{x \to -0} f(x) \neq f(0)\)のため、\(\small (*)\)が不成立となるので 関数\(\small f(x)\)は \(\small x=0\)において不連続である…【答】.
参考までに \(\small \displaystyle \lim_{x \to +0} f(x)\)(右側極限)も求めてみよう。左側極限と同様で、『\(\small x=0\)の右側からの極限』という意味なので、関数の\(\small x\)座標としては\(\small x>0\)の範囲と考えればよい。よって、\(\small x>0\)での関数 \(\small f(x)\)は
$$\small f(x)=|x|=x$$
なので、
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to +0} f(x) = \lim_{x \to +0} x=0\\
\end{split}
【考察】『右側極限=左側極限』だけでは連続とは言えない
本問では
$$\small \displaystyle \lim_{x \to -0} f(x) = \lim_{x \to +0} f(x)$$
は成り立っているが \(\small f(0)=1\)のため下図のようなグラフになり連続とはならない(=途切れている)。
このことからもわかる通り、連続性を調べるには\(\small x=a\)での左側極限・右側極限の一致に加えて\(\small f(a)\)の値とも一致するかの確認が必要である。
【問題1】連続関数になる条件(難易度:★★☆)
関数
$$\small \displaystyle f(x)=\lim_{n \to \infty}\frac{x^{2n}-x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$$
がすべての\(\small x\)に対して連続になるような定数 \(\small a, b\)の値を求めよ。
[公立はこだて未来大 改題]
・関数の連続性を確認する問題では、場合分けされた区間の境界での連続性を確認せよ。
●OnePoint
これまでに学習した多くの関数は連続関数(2次関数、三角関数、対数関数など)である。ただ、本問の極限の形で定義されている関数のように\(\small x\)の定義域によって関数の形が異なる関数が連続関数か否かを判別するためには、各定義域内の関数が区間の境界で繋がっていることを確認する必要がある。
\(\small n \to \infty\)の極限は
\begin{split}
\small \lim_{n \to \infty} x^n =
\begin{cases}
\small \infty \quad (1<x \mathsf{のとき})\\
\small 1 \quad (x=1\mathsf{のとき})\\
\small 0 \quad (|x|<1\mathsf{のとき})\\
\small \pm 1 \quad (\mathsf{振動}) \quad (x=-1 \mathsf{のとき})\\
\small \pm \infty \quad (\mathsf{振動}) \quad (x<-1 \mathsf{のとき})\\
\end{cases}
\end{split}
となるため、関数の境界となる[1]:\(\small x<-1\)、[2]:\(\small x=-1\)、[3]:\(\small -1<x<1\)、[4]:\(\small x=1\)、[5]:\(\small 1<x\)の5つのパターンで場合分けして考える。
[1] \(\small x<-1\)の場合
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{n \to \infty} \left| \frac{1}{x^n}\right|=0 \quad [*1]\\
\end{split}
より、
\begin{split}
\small f(x) &\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty} \frac{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{a}{x^{2n-2}}+\dfrac{b}{x^{2n-1}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\\
&\small \displaystyle = \frac{1-\dfrac{1}{x}+\color{#ef5350}0+\color{#ef5350}0}{1+\color{#ef5350}0}\\
&\small \displaystyle = 1-\frac{1}{x} \space \cdots ①\\
\end{split}
*1:【補足】べき乗の極限(1)
\(\small x<-1\)なのでたとえば、\(\small x=-2\)とかで具体的にイメージすると、
\begin{split}
&\small \displaystyle \left|\frac{1}{(-2)^5}\right|=\frac{1}{32}=0.03125,\\
&\small \displaystyle \left|\frac{1}{(-2)^{10}}\right|=\frac{1}{1024}≒0.00097,\\
&\small \displaystyle \left|\frac{1}{(-2)^{20}}\right|=\frac{1}{1048576}≒9.5 \times 10^{-7},\\
&\small \space \cdots\\
\end{split}
のように指数\(\small n\)を大きくするほど分母の絶対値も大きくなるので全体の値としてはどんどん0に近づいていく。最終的に\(\small n\to\infty\)の極限では分母の絶対値が無限大になるので、全体の値としては0に収束する。この感覚はしっかりと身に着けておこう!
[2] \(\small x=-1\)の場合
\(\small x\)の値が分かっているので、関数\(\small f(x)\)に代入すると
\begin{split}
\small f(-1) &\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty}\frac{(-1)^{2n}-(-1)^{2n-1}+a \cdot (-1)^2+b\cdot(-1)}{(-1)^{2n}+1}\\
&\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty}\frac{1-(-1)+a-b}{1+1} \space \color{magenta}{◀-1\mathsf{の偶数乗は}1,\mathsf{奇数乗は}-1}\\
&\small \displaystyle =\frac{a-b+2}{2} \space \cdots ② \space \color{magenta}{◀nが消えたので極限に無関係}\\
\end{split}
[3] \(\small -1<x<1\)の場合
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{n \to \infty}x^n=0 \quad [*2]\\
\end{split}
より、
\begin{split}
\small f(x) &\small \displaystyle = \frac{\color{#ef5350}0-\color{#ef5350}0+a x^2+bx}{\color{#ef5350}0+1}\\
&\small \displaystyle = a x^2+bx \space \cdots ③\\
\end{split}
*2:【補足】べき乗の極限(2)
\(\small -1<x<1\)(かっこよく書くと \(\small |x|<1\))の場合は、具体的な数字を数個イメージすればわかるが必ず「|分子|<|分母|」になる(\(\small 1/2, -4/7\)など)。よって、無限乗すると分母がどんどん大きくなるので、全体の値は0に収束する。
[4] \(\small x=1\)の場合
関数\(\small f(x)\)に代入すると
\begin{split}
\small f(1) &\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty}\frac{1^{2n}-1^{2n-1}+a \cdot 1^2+b\cdot 1}{1^{2n}+1}\\
&\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty}\frac{1-1+a+b}{1+1} \space \color{magenta}{◀1\mathsf{のべき乗は}1}\\
&\small \displaystyle =\frac{a+b}{2} \space \cdots ④ \space \color{magenta}{◀nが消えたので極限に無関係}\\
\end{split}
[5] \(\small 1<x\)の場合
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{n \to \infty} \frac{1}{x^n}=0 \quad [*3]\\
\end{split}
より、
\begin{split}
\small f(x) &\small \displaystyle = \lim_{n \to \infty} \frac{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{a}{x^{2n-2}}+\dfrac{b}{x^{2n-1}}}{1+\dfrac{1}{x^{2n}}}\\
&\small \displaystyle = \frac{1-\dfrac{1}{x}+\color{#ef5350}0+\color{#ef5350}0}{1+\color{#ef5350}0}\\
&\small \displaystyle = 1-\frac{1}{x} \space \cdots ⑤\\
\end{split}
*3:【補足】べき乗の極限(3)
本質的には *1と同じで \(\small 1<x\)の数を具体的に考えてあげれば極限値が0になることが分かるだろう。ちなみに、*1の時は\(\small x\)の値が負だったので指数の\(\small n\)乗の偶奇性によって極限をとったときの\(\small \displaystyle \frac{1}{x^n}\)の値が正にも負にもなる可能性があるため、
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{n \to \infty} \left| \frac{1}{x^n}\right|=0\\
\end{split}
のように絶対値を付けていたが、今回は\(\small 1<x\)なので正の値であることから絶対値はつけていない。
[1]~[5]の結果をまとめると下図のようになる。

ここで、①、③、⑤は連続関数(曲線がどこかで途切れたりしていない関数)であり、②、④は\(\small x=\pm1\)での関数の値なので、関数\(\small f(x)\)がすべての\(\small x\)に対して連続(つながっている)であるためには、『① ⇔ ② ⇔ ③』で連続かつ『③ ⇔ ④ ⇔ ⑤』で連続、すなわち、\(\small x=-1\)で連続かつ\(\small x=1\)で連続であることが確認できればよい。

[A] \(\small x=-1\)での連続性(『① ⇔ ② ⇔ ③』)
\(\small x=-1\)における値と右側極限、左側極限、\(\small x=-1\)における関数\(\small f(x)\)の\(\small y\)座標が一致すればよいので [*4]
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to -1-0} \left(1-\frac{1}{x}\right)=1+1=2\\
&\small \displaystyle \lim_{x \to -1+0} \left(ax^2+bx\right)=a-b\\
&\small \displaystyle f(-1)=\frac{a-b+2}{2} \quad \color{magenta}{◀ ②より}\\
\end{split}
より、
\begin{split}
&\small 2=a-b=\frac{a-b+2}{2} \quad ※\\
\small ∴ \space &\small \color{#ef5350}{a-b=2 \space \cdots ⑥}\\
\end{split}
※3つの式がイコールで結ばれているが、どの2つを選んでも⑥と同じ関係式になる
*4:【補足】右側極限・左側極限
\(\small x=-1\)の左側極限とは、読んで字の如く左側から限りなく\(\small x=-1\)に近づけたときの極限値のこと。\(\small x=-1\)よりちょっと小さいという意味を込めて \(\small \color{red}{x \to -1-0}\)で表現する。『\(\small -1-0\)』という表現が分かりにくいが、\(\small -1\)からほぼ0を引き算する(イメージとしては\(\small x=-1-0.00001\)みたいな感じ)ことを表している。
\(\small x \to -1-0\)は\(\small x=-1\)より小さい範囲なので、関数\(\small f(x)\)としては\(\small x<-1\)の範囲の\(\small \displaystyle f(x)=1-\frac{1}{x}\)を用いる必要があるので、左側極限は\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1-0} \left(1-\frac{1}{x}\right)\)となる。
右側極限も同様に\(\small x=-1\)より少し大きな値を\(\small x \to -1+0\)で表しており、\(\small x=-1\)より少し大きいだけなので関数としては\(\small -1<x<1\)の範囲で考えればよい(\(\small 1<x\)にはならない)ので\(\small f(x)=ax^2+bx\)を用いて右側極限は\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1+0} \left(ax^2+bx\right)\)となる。
[B] \(\small x=1\)での連続性(『③ ⇔ ④ ⇔ ⑤』)
同様に\(\small x=1\)における値と右側極限、左側極限、\(\small x=1\)における関数\(\small f(x)\)の\(\small y\)座標が一致すればよいので
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 1-0} \left(ax^2+bx\right)=a+b\\
&\small \displaystyle \lim_{x \to 1+0} \left(1-\frac{1}{x}\right)=1-1=0\\
&\small \displaystyle f(1)=\frac{a+b}{2} \quad \color{magenta}{◀ ④より}\\
\end{split}
より、
\begin{split}
&\small \displaystyle a+b=0=\frac{a+b}{2}\\
\small ∴ \space &\small \color{#ef5350}{a+b=0 \space \cdots ⑦}
\end{split}
よって、\(\small x=-1\)で連続かつ\(\small x=1\)で連続であるためには、⑥かつ⑦が成り立てばよいので、⑥、⑦を連立することで、
\begin{cases}
\small a-b=2\\
\small a+b=0\\
\end{cases}
ゆえに、\(\small a=1, \space b=-1\)…【答】.
【問題2】関数の連続性の確認(難易度:★★☆)
\begin{split} \small f(x)= \begin{cases} \small \displaystyle \frac{|x^2-1|}{x-1} \quad (x \neq 1)\\ \small \displaystyle 0 \qquad \quad \space \space \space (x = 1)\\ \end{cases} \end{split} で定義される関数について、\(\small x=-1\)および\(\small x=1\)での連続性を調べよ。
・本問の関数は絶対値が含まれているので、絶対値を外すことで各区間における関数の形を求めることがポイント。
関数の中に絶対値が含まれると計算しにくいので、場合分けすることで絶対値を外すことを考える。
絶対値の中身が0以上になるような\(\small x\)の範囲は
\begin{split}
&\small x^2-1≧0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (x-1)(x+1)≧0\\
\small ∴ \space &\small x≦-1, \space 1≦x\\
\end{split}
なので、
\begin{split}
\small |x^2-1|=
\begin{cases}
\small \quad x^2-1 \quad (x≦-1, \space 1≦x)\\
\small -(x^2-1) \quad (-1<x<1)\\
\end{cases}
\space [*1]
\end{split}
*1:【補足】絶対値の外し方
絶対値の中身が負のときは、符号をとると考えるのではなく、\(\small |-2|=-(-2)=2\)のように中身の値にマイナスをつけると考えてあげればよかったので、一般的に\(\small |A|\)の値は、
\begin{split}
\small |A|=
\begin{cases}
\small \space \space A \quad (A≧0)\\
\small -A \quad (A<0)\\
\end{cases}
\end{split}
よって、関数 \(\small f(x)\)は次の4パターンに場合分けできる。
[1] \(\small x<-1, \space 1<x\)のとき
\begin{split}
\small f(x) &\small \displaystyle =\frac{x^2-1}{x-1}\\
&\small = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}\\
&\small = x+1 \space \cdots ①\\
\end{split}
[2] \(\small x=-1\)のとき
\begin{split}
\small \displaystyle f(-1)= \frac{|(-1)^2-1|}{(-1)-1}=0 \space \cdots ②
\end{split}
[3] \(\small -1<x<1\)のとき
\begin{split}
\small f(x) &\small \displaystyle =\frac{-(x^2-1)}{x-1}\\
&\small = -\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}\\
&\small = -x-1 \space \cdots ③\\
\end{split}
[4] \(\small x=1\)のとき
関数の定義より、\(\small x=1\)のときは
\begin{split}
\small \displaystyle f(1)=0 \space \cdots ④
\end{split}
よって、各区間における関数は以下のように整理できる。
\begin{split}
\small f(x)=
\begin{cases}
\small \space \space x+1 \quad (x<-1, \space 1<x)\\
\small \quad 0 \qquad (x= \pm 1)\\
\small -x-1 \quad (-1<x<1)\\
\end{cases}
\end{split}
●OnePoint
関数が簡単なので定義域に気を付けてグラフの概形を図示するとグラフから\(\small x=-1\)で連続(線がつながっている)、\(\small x=1\)で不連続(線がつながっていない)であることが感覚的にわかる。ただ、厳密ではないので、このあとの論証で右側極限と左側極限を調べて\(\small y\)座標の一致・不一致を確認する必要がある。
では、ここから\(\small x=-1\)、\(\small x=1\)における関数の連続性についてそれぞれ確認する。
☆\(\small x=-1\)における連続性の確認
\(\small x=-1\)よりちょっと左側の範囲では関数 \(\small f(x)\)は①が適用される(\(\small x<-1\)の範囲なので)ので、左側極限は
\begin{split}
\small \lim_{x \to -1-0} f(x) &\small =\lim_{x \to -1-0} (x+1)\\
&\small =-1+1\\
&\small =\color{#ef5350}0\\
\end{split}
一方で、\(\small x=-1\)よりちょっと右側の範囲では関数 \(\small f(x)\)は③が適用される(\(\small -1<x<1\)の範囲なので)ので、右側極限は
\begin{split}
\small \lim_{x \to -1+0} f(x) &\small =\lim_{x \to -1+0} (-x-1)\\
&\small =-(-1)-1\\
&\small =\color{#ef5350}0\\
\end{split}
よって、右側極限と左側極限が一致することから \(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)=0\)が成り立ち、この極限値が②より\(\small x=-1\)での関数の\(\small y\)座標 \(\small f(-1)=0\)とも一致することから、\(\small x=-1\)において関数\(\small f(x)\)は連続である.
☆\(\small x=1\)における連続性の確認
同様に、\(\small x=1\)よりちょっと左側の範囲では関数 \(\small f(x)\)は③が適用される(\(\small -1<x<1\)の範囲なので)ので、左側極限は
\begin{split}
\small \lim_{x \to 1-0} f(x) &\small =\lim_{x \to 1-0} (-x-1)\\
&\small =-1-1\\
&\small =\color{#ef5350}{-2}\\
\end{split}
一方で、\(\small x=1\)よりちょっと右側の範囲では関数 \(\small f(x)\)は①が適用される(\(\small 1<x\)の範囲なので)ので、右側極限は
\begin{split}
\small \lim_{x \to 1+0} f(x) &\small =\lim_{x \to 1+0} (x+1)\\
&\small =1+1\\
&\small =\color{#ef5350}2\\
\end{split}
よって、右側極限と左側極限が一致しないことから \(\small \displaystyle \lim_{x \to 1}f(x)\)の極限が存在せず、④の\(\small x=1\)における関数の\(\small y\)座標 \(\small f(1)=0\)とも不一致であることから、\(\small x=1\)において関数\(\small f(x)\)は不連続である.
よって、関数 \(\small f(x)\)は\(\small x=-1\)において連続、\(\small x=1\)において不連続である…【答】.
【補足】 \(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)\)や \(\small \displaystyle \lim_{x \to 1}f(x)\)の意味は?
最初は少しわかりにくいが、、\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)\)を例に一つずつ数式の意味を紐解いてみよう。関数 \(\small f(x)\)は端的に言うと関数の\(\small y\)座標の値だ。そして、\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}\)は\(\small x\)座標が限りなく-1に近い、すなわち\(\small x=-1\)付近ということを表している。つまり、\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)\)は、『\(\small x=-1\)付近の点における関数の\(\small y\)座標の値』という意味を表している。
なので、\(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)\)と\(\small f(-1)\)(\(\small x=-1\)における\(\small y\)座標)が一致していれば、\(\small x=-1\)とその付近において関数の\(\small y\)座標が一致していることになるので、連続(つながっている)が確認できるわけである。そして、本問では極限 \(\small \displaystyle \lim_{x \to -1}f(x)\)を計算するにあたり、\(\small x=-1\)の右側と左側で関数が異なるので右側極限と左側極限にそれぞれ分けて考えてあげて極限値が一致することを確認している。
本記事のまとめ
今回は関数の連続性に関して徹底解説していきました。問題を通して、『連続とは何か』、『右側極限・左側極限とは何か』、『関数の連続性を確認する方法』が理解できたでしょうか?
最後に本記事の重要ポイントを復習して終わりにしましょう!
☆重要ポイント☆
≪連続ってなに?≫
・連続とは関数がつながっていること。
≪右側極限・左側極限ってなに?≫
・右側極限とは、特定の\(\small x\)座標のちょっと右側での\(\small y\)の値のこと。
(左側極限であれば、ちょっと左側での\(\small y\)の値)
≪関数の連続性の確認方法は?≫
・関数\(\small f(x)\)が\(\small x=a\)で連続であるとは
\begin{split}
\small \color{red}{\lim_{x \to a-0} f(x)} &\small \color{red}{=f(a)=\lim_{x \to a+0} f(x)}\\
\end{split}
が成り立つこと。
⇒『「左側極限値」 \(\small =\) 「\(\small x=a\)での\(\small y\)座標」 \(\small =\) 「右側極限値」』を確認!
今回はここまでです。お疲れさまでした!
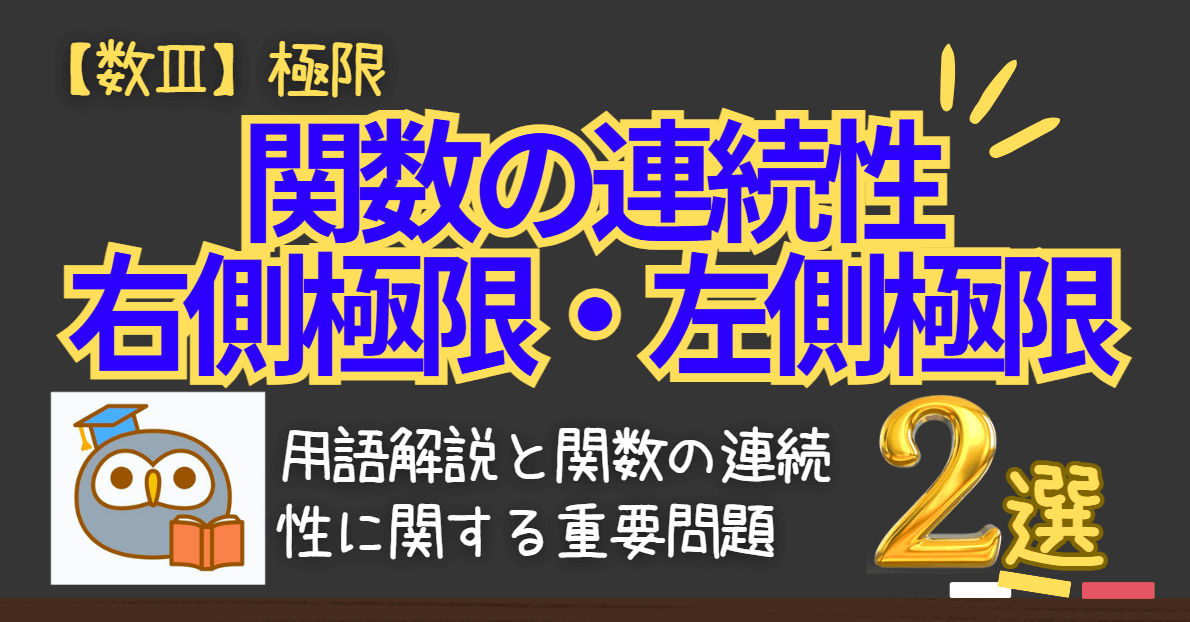
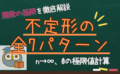
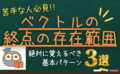


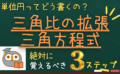
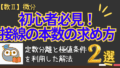
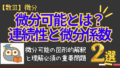
コメント