今回は微分係数の定義と平均値の定理を利用して極限値を求める問題について解説していきます。この分野は、「微分係数の定義が利用できそうだからうまく式変形して解こう」といったように、ある程度の問題慣れや経験、ひらめきがないと解けないんでしょ…と思われがちです。ですが、実は誰でも解ける裏ワザ的解法が存在します!
そこで本記事では、微分係数の定義や平均値の定理を利用して極限を求める問題の特徴とどちらを使うかの見極めのコツ、そしてひらめきや経験に依らずに解ける裏ワザ的解法を徹底解説していこうと思います。実践問題を通してぜひ問題を解くコツを身に着けていきましょう!
- 微分係数の定義、平均値の定理を利用して極限を求める問題の解き方を理解したい人
- 微分係数の定義または平均値の定理のどちらを使うかの見極めのコツを知りたい人
- 極限の応用問題を通して実践的な力をアップさせたい人
- 大学入試対策、定期テスト対策がしたい人
【基礎講義】微分係数・平均値の定理を利用した極限値
【講義1】裏ワザあり!!微分係数の定義を利用した極限
そもそも極限の計算に微分係数が利用できるのはなぜか?を考えると、その理由は微分係数の定義式に極限が含まれるからでした。
上記の定義式を利用するために、うまく関数\(\small f(x)\)を見つけてくる解法が一般的ですが、ここでは微分係数の定義が利用できるか否かの見極め方法と、利用できる場合の非常にシンプルな裏ワザ的解法を解説します。
・極限をそのまま計算すると分母・分子が\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になる場合、微分係数の定義が利用できる!
≫極限値の求め方 ※裏ワザあり
・分母または分子を丸ごと関数 \(\small f(x)\)とおくことで、微分係数の定義を適用せよ!
これだけだと分かりにくいと思うので、例題を通して具体的なイメージを確認していきましょう。
\(\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{2^x-1}{x}\)の極限値を求めよ。
一般的な解法
関数 \(\small f(x)=2^x\)とおくと、問題の極限は
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{2^x-2^0}{x-0}\\
\small =&\small \lim_{x \to \color{red}0}\frac{f(x)-f(\color{red}0)}{x-\color{red}0}\quad \color{magenta}{◀微分係数の定義の形}\\
\small =&\small f^\prime (\color{red}0) \\
\end{split}
\(\small f^\prime (x) =2^x \log 2\)より、\(\small f^\prime (0)= \log 2\)…【答】.
【考察】
一般的な解法では、微分係数の定義式
$$\small \displaystyle \lim_{x \to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f^\prime (a)$$
を満たすような関数\(\small f(x)\)をうまく見つけてくる必要がある。
例題の場合は分かりやすいが、問題によっては見つけるのが大変…。
裏ワザ的解法
問題の極限をそのまま計算すると、分母分子ともに『0』となるため\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になる。
よって、分子を丸ごと \(\small f(x) = 2^x -1\)と置けば\(\small f(0)=2^0-1=0\)になるので、微分係数の定義を適用させることで、
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{\color{#ef5350}{(2^x-1)}-\color{#5c6bc0}0}{x-0}\\
\small =&\small \lim_{x \to 0}\frac{\color{#ef5350}{f(x)}-\color{#5c6bc0}{f(0)}}{x-0}\quad \color{magenta}{◀微分係数の定義の形}\\
\small =&\small f^\prime (0) \\
\end{split}
よって、\(\small f^\prime (x) =2^x \log 2\)より、\(\small f^\prime (0)= \log 2\)…【答】.
このように、裏技的解法では、求める極限の関数が\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形であるならば、分母または分子をひとまとまりの関数とおくことで、必ず微分係数の定義式を利用できる形になるため、うまい式変形を考えることなく機械的に解くことができる点がメリットとなる。
【講義2】平均値の定理を利用した極限
はじめに、平均値の定理をおさらいしておきましょう。
$$\small \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$
となる実数\(\small c\)が\(\small a<c<b\)の範囲に存在する。
平均値の定理の意味や詳しい解説については、「【数III】平均値の定理を利用した不等式の証明(式変形のコツを入試問題で徹底解説)」の記事をチェックしよう!
平均値の定理は『同じ関数の差』の形がある点がポイント!例えば、求める極限に\(\small \cos (x+a)-\cos a\)のような形が含まれていたら、関数の引数が\(\small x\)か\(\small x+a\)かの違いだけでどちらも同じ関数\(\small \cos x\)なので、平均値の定理を利用して極限値を求める問題と判断してもよいでしょう。
一方で、平均値の定理は微分係数の定義式とは異なり、どこにも極限が出てこないので、「平均値の定理を使ってどうやって極限を求めるの?」という疑問が湧き上がってくるでしょう。
実は平均値の定理を利用して極限を求める問題では、『 \(\small a < c < b\) 』という実数\(\small c\)の存在範囲を利用してはさみうちの原理から極限値を求める方針になります。

この説明だけだと分かりにくいと思うので、詳細は実際の問題を解く中で感覚を掴んでいくとよいでしょう(【問題3】平均値を利用した極限値)。
・求める極限に同じ関数の差の形が含まれる場合、平均値の定理が利用できる!
≫極限値の求め方
・\(\small a < c < b\)の不等式を利用することではさみうちの原理で極限値を求める。
【問題&解説】極限値を求める応用問題
【問題1】微分係数の定義を利用した極限値(難易度:★★☆)
次の極限を求めよ。
(1)\(\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{e^{2x}-1}{x}\)
(2)\(\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\sin (x+a) – \sin a}\)
(3)\(\small \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{x^2 \log 2 -\log x^4}{x^2-4}\)
問題の関数に対してそのまま極限をとると
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{e^{2x}-1}{x}\\
&\small = \displaystyle \frac{1-1}{0}\\
&\small = \displaystyle \color{#ef5350}{\frac{0}{0}}\\
\end{split}
の不定形になる。よって、分子を \(\small f(x)=e^{2x}-1\)とおくことで、\(\small f(0)=1-1=0\)であることから
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{(e^{2x}-1)-0}{x-0}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \quad \color{magenta}{◀微分係数の定義の形}\\
&\small = \displaystyle f^\prime (0)\\
\end{split}
よって、\(\small f^\prime (x) =2e^{2x}\)より、\(\small f^\prime (0)=2\)…【答】.
【補足】
一般的な回答としては、\(\small f(x)=e^{2x}\)とおいて
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0} 2\cdot \frac{e^{2x}-1}{2x}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} 2\cdot \frac{e^{2x}-e^0}{2x-0}\\
&\small = \displaystyle f^\prime (0)\\
\end{split}
のような少しトリッキーな式変形をする必要がありますが、裏ワザで紹介した解法であればそのような考慮は不要で、機械的に分子全体を \(\small f(x)\)とおいてしまえばよいので簡単ですね。
問題の関数に対してそのまま極限をとると、
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\sin (x+a) – \sin a}\\
&\small = \displaystyle \frac{\sin 0}{\sin a-\sin a}\\
&\small = \displaystyle \frac{0}{0}\\
\end{split}
ここで、分母を丸ごと \(\small f(x)=\sin (x+a)-\sin a\)とおくと、\(\small f(0)=\sin a-\sin a=0\)であることから、
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\sin (x+a) – \sin a}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{f(x)}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{f(x)\color{#ef5350}{-f(0)}} \quad \color{magenta}{◀ f(0)=0}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\color{#ef5350}x}\cdot \frac{\color{#ef5350}x}{f(x)-f(0)}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\cdot \dfrac{1}{\color{#ef5350}{\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}}}\quad \color{magenta}{◀微分係数の定義の形}\\
&\small = \frac{1}{\color{#ef5350}{f^\prime (0)}}\\
\end{split}
ただし、最後の極限の計算は
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} =1\\
\end{split}
の関係式を用いた。
よって、\(\small f^\prime (x) = \cos (x+a)\)より、
$$\small \displaystyle \frac{1}{f^\prime (0)}=\color{red}{\frac{1}{\cos a} \space \cdots 【答】}$$
【参考】関数は丸ごと\(\small f(x)\)とおこう!
解答では、\(\small \sin (x+a)-\sin a\)を丸ごと\(\small f(x)\)と置きましたが、経験を積んでいる人であれば\(\small \sin (x+a)-\sin a\)の形から、\(\small f(x)=\sin x\)として
$$\small \displaystyle \lim_{h \to 0}\frac{f(h+a)-f(a)}{h}=f^\prime (a) \space \cdots (*)$$
の微分係数の定義を利用することで
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{\sin (x+a) – \sin a}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\cdot \dfrac{1}{\color{#ef5350}{\dfrac{\sin (x+a) – \sin a}{x}}}\\
&\small = \displaystyle \left. 1 \cdot \dfrac{1}{\color{#ef5350}{(\sin x)^\prime}}\right |_{x=a} \space ◀微分した関数に x=aを代入\\
&\small = \displaystyle \frac{1}{\cos a}\\
\end{split}
と解いた人もいたでしょう。もちろんこの解答も正解なのですが、極限を求める点においては、\(\small (*)\)の形の微分係数の定義も分子を丸ごと\(\small g(x)=f(x+a)-f(a)\)とおいてしまえば、\(\small \color{#ef5350}{g(0)}=f(a)-f(a)=\color{#ef5350}0\)となるので
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{f(x+a)-f(a)}{x}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{g(x)}{x}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0} \space \color{magenta}{◀g(0)=0}\\
&\small =g^\prime (0)\\
\end{split}
となることから、上式の3行目と4行目の等号は微分係数の定義式
$$\small \displaystyle \lim_{x \to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f^\prime (a)$$
の\(\small a=0\)の場合に相当します。
そのため、微分係数の定義式が2種類あってどちらの形を適用すればよいかを考えなくても、裏技的解法である『分子または分母を丸ごと関数とおく』解法でどんなパターンでも解くことができます。
問題の関数に対してそのまま極限をとると、
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{x^2 \log 2 -\log x^4}{x^2-4}\\
&\small = \displaystyle \frac{4 \log 2 -\log 2^4}{4-4}\\
&\small = \displaystyle \frac{\log 16 -\log 16}{4-4}\\
&\small = \displaystyle \frac{0}{0}\\
\end{split}
の不定形になることから、分子を \(\small f(x)=x^2 \log 2 – \log x^4\)とおくことで、\(\small f(2)=\log 16 -\log 16=0\)であることから
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{x^2 \log 2 -\log x^4}{x^2-4}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{(x+2)(x-2)}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{f(x)-f(2)}{(x+2)(x-2)} \space \color{#ef5350}{(∵ f(2)=0)}\\
&\small = \displaystyle \lim_{x \to 2} \color{#ef5350}{\frac{f(x)-f(2)}{x-2}}\cdot \frac{1}{x+2}\\
&\small = \displaystyle \color{#ef5350}{f^\prime (2)}\cdot \frac{1}{4} \space \cdots ①\\
\end{split}
ここで、\(\small f(x)\)を微分しやすいように\(\small f(x)= x^2 \log2 -4 \log x\)のように式変形しておくと
\begin{split}
&\small \displaystyle f^\prime (x) =2x \log2 -\frac{4}{x}\\
\small ∴ \space &\small \displaystyle f^\prime (2) =4 \log2 -2\\
\end{split}
よって、①に代入することで求める極限値は、
\begin{split}
\small \displaystyle \frac{f^\prime (2)}{4} &\small =\frac{4 \log2 -2}{4}\\
&\small =\color{red}{\log2-\frac{1}{2} \space \cdots 【答】}\\
\end{split}
【別解】
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 2} \frac{x^2 \log 2 -\log x^4}{x^2-4}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 2} \frac{(x^2-4) \log 2+4\log 2 -4\log x}{x^2-4}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 2} \left[ \frac{(x^2-4) \log 2}{x^2-4}+\frac{4\log 2 -4\log x}{x^2-4}\right]\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 2} \left[ \log 2-4\frac{\log x-\log 2}{(x-2)(x+2)}\right]\\
&\small \displaystyle =\log 2 -4 \lim_{x \to 2}\color{#ef5350}{\frac{\log x-\log 2}{x-2}}\cdot \frac{1}{x+2}\\
\end{split}
赤字箇所について、\(\small f(x)=\log x\)とおくと、
$$\small \displaystyle \lim_{x \to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f^\prime (2)$$
より、\(\small \displaystyle f^\prime (x)=\frac{1}{x}\)、すなわち\(\small \displaystyle f^\prime (2)=\frac{1}{2}\)となることから、求める極限は
\begin{split}
&\small \displaystyle \log 2 -4\cdot \color{#ef5350}{\frac{1}{2}}\cdot \frac{1}{2+2}\\
&\small \displaystyle =\log 2 -\frac{1}{2}\\
\end{split}
【問題2】微分係数を用いて極限値を表す問題(難易度:★★☆)
\(\small \displaystyle \lim_{x \to a}\frac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x^2-a^2}\)の値を\(\small a\),\(\small f(a)\),\(\small f^\prime (a)\)を用いて表せ。
[弘前大]
\(\small g(x)=x^2f(x)-a^2f(a)\)とおく。\(\small g(a)=a^2f(a)-a^2f(a)=0\)…①より、
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to a}\frac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x^2-a^2}\\
&\small \displaystyle = \lim_{x \to a}\frac{g(x)}{(x-a)(x+a)}\\
&\small \displaystyle = \color{#ef5350}{\lim_{x \to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}}\cdot \frac{1}{x+a} \space ◀ ∵① \space g(a)=0\\
&\small \displaystyle = \color{#ef5350}{g^\prime (a)} \cdot \frac{1}{a+a}\\
&\small \displaystyle = \frac{g^\prime (a)}{2a} \space \cdots ②\\
\end{split}
ここで、
\begin{split}
&\small \displaystyle g^\prime (x) =2xf(x)+x^2f^\prime (x) \quad [*1]\\
\small ∴ \space &\small \displaystyle g^\prime (a) =2af(a)+a^2f^\prime (a)\\
\end{split}
*1:【補足】関数の積の微分
第1項目は
$$\small (f(x)g(x))^\prime =f^\prime(x)g(x)+f(x)g^\prime(x)$$
の公式を利用。第2項目の\(\small a^2f(a)\)は\(\small x\)の関数ではないので微分すると0になる。
より、②に代入することで
\begin{split}
\small \displaystyle \frac{g^\prime (a)}{2a} &\small =\frac{2af(a)+a^2f^\prime (a)}{2a}\\
&\small \displaystyle =\color{red}{f(a)+\frac{af^\prime (a)}{2} \space \cdots 【答】}\\
\end{split}
【考察】
以下のようにうまく微分係数の定義式が適用できるような形に式変形して解くこともできる。
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to a}\frac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x^2-a^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to a}\frac{x^2f(x)\color{#ef5350}{-x^2f(a)+x^2f(a)}-a^2f(a)}{x^2-a^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to a}\frac{x^2(f(x)-f(a))+(x^2-a^2)f(a)}{x^2-a^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to a}\frac{x^2}{x+a} \cdot \frac{f(x)-f(a)}{x-a}+f(a)\\
&\small \displaystyle =\frac{a^2}{2a} f^\prime (a)+f(a)\\
&\small \displaystyle =\frac{af^\prime (a)}{2} +f(a)\\
\end{split}
【問題3】平均値を利用した極限値(難易度:★★☆)
次の極限を求めよ。
(1)\(\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{e^{x}-e^{x^2}}{x-x^2}\)
(2)\(\small \displaystyle \lim_{x \to \infty} x \{\log(x+2)-\log x\}\)
→考え方は講義2_平均値の定理を利用した極限を参照。
・(2)で\(\small x \to \infty\)での\(\small f^\prime (c)\)の値は、実数\(\small c\)の存在範囲 \(\small x < c < x+2\)に対して、はさみうちの原理を利用して求めるのが定石。
あえて回答に書く必要はないが、単純に\(\small x \to 0\)の極限をとっても\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になるため、何かしらの式変形が必要というのがそもそものスタート地点になる。
求める極限の\(\small e^x – e^{x^2}\)に着目すると、\(\small f(x)=e^x\)と見なすことで \(\small f(x)-f(x^2)\)となり同じ関数の差の形が含まれていることが分かる(関数の中身の引数が違うだけ)。
よって、平均値の定理が利用できないか検討してみよう。すると、分母にも関数と同じ引数の差(\(\small x-x^2\)の形)があることから、平均値の定理が使えそうだ。
関数\(\small f(x)=e^x\)は連続かつ微分可能なので、平均値の定理より
$$\small \displaystyle \frac{e^x-e^{x^2}}{x-x^2}=e^c \space \cdots ①$$
また、実数\(\small c\)は\(\small x^2 <c <x\)または\(\small x<c<x^2\)…② を満たす [*1]。
*1:【補足】平均値の定理との対応
平均値の定理がどう利用されているのかやや分かりにくいが、\(\small x^2=a\)、\(\small x=b\)とおいてあげると、
$$\small \displaystyle \frac{e^b-e^{a}}{b-a}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$
となり平均値の定理の左辺と一致することが分かる。右辺は、\(\small f(x)=e^x\)とおいているので、\(\small f^\prime (x)=e^x\)より、\(\small f^\prime(c)=e^c\)。
よって、
$$\small \displaystyle \frac{e^b-e^{a}}{b-a}=e^c$$
が成り立つことが分かる。
また、実数\(\small c\)の範囲については、\(\small a<c<b\) に冒頭の \(\small a=x^2\)、\(\small b=x\)を代入すれば\(\small x^2 <c <x\)を満たすことが分かる。
②の実数 \(\small c\)が満たす範囲は、\(\small x\)の値によって\(\small x\)と\(\small x^2\)の大小関係が変わる点に注意しよう。
\(\small x^2 < x\)となる条件は、
\begin{split}
&\small x^2 < x\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x^2 -x <0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x(x-1) <0\\
\small ∴ \space &\small \color{#ef5350}{0<x<1}\\
\end{split}
逆に、\(\small x< x^2\)となる条件は、\(\small x<0,\space 1<x\)となる。
本問では \(\small x \to 0\)の極限、すなわち\(\small x=0\)付近を考えているため、\(\small x\)の値が0よりちょっと大きいか小さいかで\(\small x\)と\(\small x^2\)の大小関係が変わってくるが、いずれの場合も \(\small x \to 0\)の極限では
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0} x = 0\\
&\small \lim_{x \to 0} x^2 = 0\\
\end{split}
であることから、はさみうちの原理より\(\small c = 0\)となることは変わらない[*2]。よって、\(\small x \to 0\)の極限では、\(\small c = 0\)となる。
*2:【補足】\(\small c =0\)になる理由
[i] \(\small x^2 < c<x\)の場合
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0}x^2 ≦ c ≦ \lim_{x \to 0}x\\
&\small \Leftrightarrow \space 0≦ c ≦ 0\\
&\small ∴ \space \color{#ef5350}{c = 0}\\
\end{split}
[ii] \(\small x < c< x^2\)の場合
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0}x ≦ c ≦ \lim_{x \to 0}x^2\\
&\small \Leftrightarrow \space 0≦ c ≦ 0\\
&\small ∴ \space \color{#ef5350}{c = 0}\\
\end{split}
ゆえに、①の式の両辺に対して\(\small x \to 0\)の極限をとると
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to 0} \frac{e^x-e^{x^2}}{x-x^2} &\small =\lim_{x \to 0} e^c\\
&\small =e^\color{magenta}0 \space \color{magenta}{◀ x \to 0ではc =0}\\
&\small = \color{red}{1 \space \cdots 【答】}\\
\end{split}
【考察】微分係数の定義式を利用した別解
『\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形』ということは、講義1でも解説した通り微分係数の定義式を利用して極限を求めることができるので、ここでは略解を紹介しておこう。
裏技的解法より、分子をまるごと\(\small f(x)=e^x-e^{x^2}\)とおくと、\(\small f(0)=1-1=0\)より、
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{f(x)}{x-x^2}=\lim_{x \to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-x^2}\\
\end{split}
あとは、微分係数の定義式
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}
\end{split}
の形に寄せるためにうまく変形していくと
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-x^2} &\small =\lim_{x \to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x(1-x)}\\
&\small =\lim_{x \to 0}\color{#ef5350}{\frac{f(x)-f(0)}{x-0}}\cdot \frac{1}{1-x}\\
&\small =\color{#ef5350}{f^\prime (0)}\cdot \frac{1}{1-0} \space \cdots ①\\
\end{split}
関数 \(\small f(x)\)の微分は、
\begin{split}
\small \displaystyle f^\prime (x) = e^x-2xe^{x^2}
\end{split}
より、\(\small f^\prime (0) = 1\)となるので、①に代入することで極限が求まる。
求める極限の『\(\small \log (x+2)-\log x\)』に着目すると同じ関数の差の形になっていることから、平均値の定理を利用して極限を求める方針で考える。
はじめに、式変形の方向性を掴むために本問の場合で平均値の定理を適用した式をかいておく。
関数 \(\small f(x)=\log x\)は連続かつ微分可能なので、平均値の定理より
\begin{split}
\small \displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^\prime (c)\\
\end{split}
において、\(\small f(x)=\log x\), \(\small b=x+2\), \(\small a= x\)を適用すればよいので
\begin{split}
&\small \displaystyle \frac{f(x+2)-f(x)}{(x+2)-x}=f^\prime (c)\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \frac{\log(x+2)-\log x}{2}=\frac{1}{c} \space \cdots ①\\
\end{split}
ただし、右辺は\(\small \displaystyle f^\prime (x) =(\log x)^\prime = \frac{1}{x}\)を用いた。また、実数\(\small c\)は、\(\small x < c <x+2\)…②を満たす[*1]。
*1:【補足】実数 \(\small c\)の範囲
(1)では \(\small x\)と\(\small x^2\)の大小関係が\(\small x\)の値によって変わったので場合分けが必要だったが、今回は\(\small x\)の値に依らずに常に\(\small x < x+2\)の大小関係が成り立つので、場合分けは不要。
では、実際に求める極限
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}x \{\log(x+2)-\log x\}\\
\end{split}
を①の左辺に近付くように式変形していこう。
\begin{split}
\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}x \{\log(x+2)-\log x \} &\small =\lim_{x \to \infty} x \cdot \color{#ef5350}{\frac{\log(x+2)-\log x}{2}}\cdot 2\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} 2x \cdot \color{#ef5350}{\frac{1}{c}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} \frac{2x}{c} \space \cdots ③\\
\end{split}
ここで②の関係式より、
\begin{split}
&\small \displaystyle x < c < x+2\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \frac{1}{x+2} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x} \quad [*2]\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \frac{2x}{x+2} < \frac{2x}{c} < \frac{2x}{x} \quad [*2]\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x+2} ≦ \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{c} ≦ \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x}\\
\end{split}
*2:【補足】式変形について
2行目の逆数をとる部分は、分母の \(\small x , \space x+2\)が0にならないことの確認が必要だが、求める極限は\(\small x \to \infty\)なので\(\small x \neq 0, \space x \neq -2\)と考えてよい。
3行目の不等式全体に\(\small 2x\)を掛け算する際も、\(\small 2x\)の符号によって不等号の向きが変化するが、\(\small x \to \infty\)であることから\(\small x>0\)と考えてよい。
不等式の両端の極限は
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x+2} \\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty}\frac{2}{1+\dfrac{2}{x}}=2\\
&\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x} =2 \\
\end{split}
なので、はさみうちの原理より
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x+2} ≦ \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{c} ≦ \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{x}\\
&\small \displaystyle \Leftrightarrow \space 2≦ \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{c}≦ 2\\
&\small \displaystyle ∴ \space \lim_{x \to \infty}\frac{2x}{c}= \color{red}{2 \space \cdots 【答】}\\
\end{split}
本記事のまとめ
今回は極限の応用問題として、微分係数の定義と平均値の定理を利用して極限を求める問題について解説しました。本記事を通して、式変形の裏ワザや微分係数の定義式を使うのか平均値の定理を使うのかの見極め方法について理解を深めることができたでしょうか?
最後に本記事のポイントをおさらいして終わりにしましょう。
☆重要ポイント☆
≪微分係数の定義式を利用した極限≫
・\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形の場合に利用できる。
・分母または分子を丸ごと関数 \(\small f(x)\)と置いて微分係数の定義を利用することで極限を求める。
≪平均値の定理を利用した極限≫
・『同じ関数の差』の形がある場合に利用できる。
・平均値の定理で出てくる実数\(\small c\)の存在範囲 \(\small a < c <b\)に対してはさみうちの原理を利用することで極限を求める。
では今回はここまでです。お疲れさまでした!
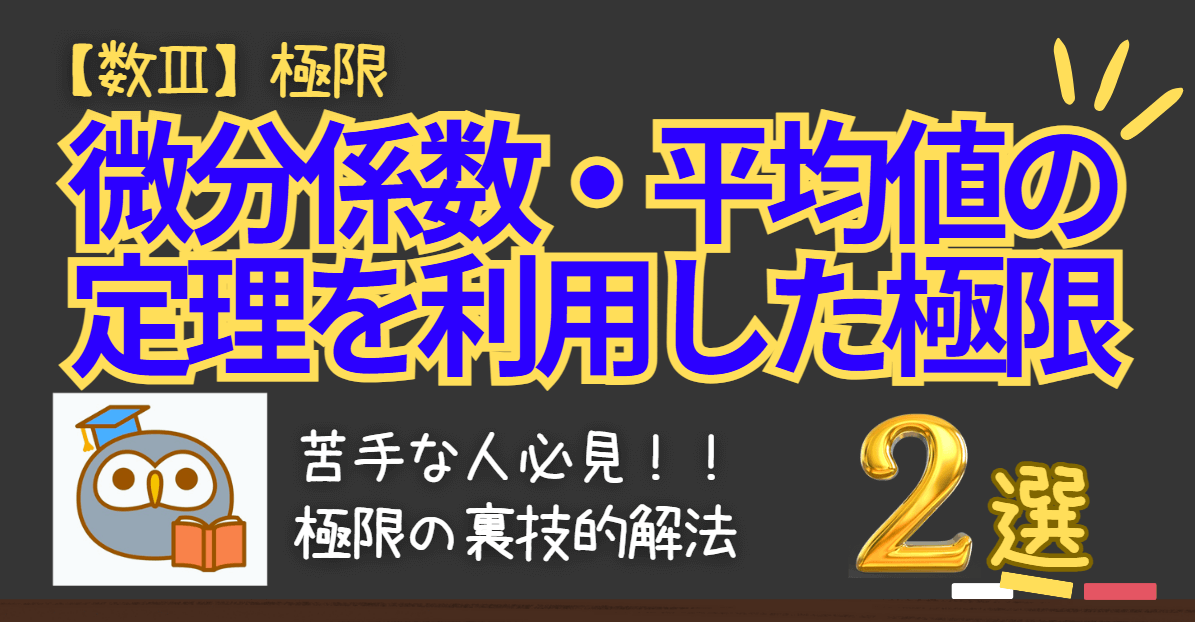
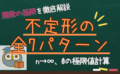
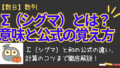
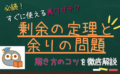

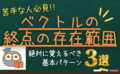
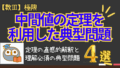
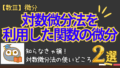
コメント