今回は極限を含む等式が有限値に収束するための必要条件を用いて未定係数を決定する問題について徹底解説していきます。必要条件を理解するには不定形の考え方を理解していなければいけないこともあり、大学入試でも取り上げられることが多い問題なので、本記事を通して考え方をしっかり理解して解けるようにしておきましょう。
- 極限が収束する条件と不定形の関係について知りたい人
- 極限を含む等式の未定係数を決定する問題の解き方を知りたい人
- 大学入試対策、定期テスト対策がしたい人
【基礎講義】不定形と極限が収束するための必要条件
【講義1】不定形とは?
まずは極限の不定形について簡単に復習しておきましょう。
不定形とは、極限の値がどんな値になるかが定まっていない形のことです。この説明だけだとどういうことかピンと来ないと思うので、分かりやすい具体例で説明します。
たとえば
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0} \frac{(2+3^x)x}{x}, \quad \lim_{x \to 0} \frac{(2-3^x)x}{x}, \quad \lim_{x \to 0} \frac{(2-3^x)x}{x^2}\\
\end{split}
の3つの極限を考えるとします。何も式変形せずにそのまま極限をとってしまうといずれも\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)となってしまいますが、しっかりと約分してから極限をとってあげれば
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0} \frac{(2+3^x)x}{x}\\
&\small =\lim_{x \to 0} (2+3^x)\\
&\small =2+1\\
&\small =\color{red}3\\
\end{split}
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0} \frac{(2-3^x)x}{x}\\
&\small =\lim_{x \to 0} (2-3^x)\\
&\small =2-1\\
&\small =\color{red}1\\
\end{split}
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0} \frac{(2-3^x)x}{x^2}\\
&\small =\lim_{x \to 0}\frac{(2-3^x)}{x}\\
&\small =\frac{1}{0}\\
&\small =\color{red}\infty\\
\end{split}
となり、それぞれ異なる値に収束もしくは発散することがわかります。このように一見すると同じ値に見えて実は極限の値が異なる形のことを不定形というわけです。
このような不定形はいくつかパターンがありますが、極限が収束するような未定係数を決定する問題では\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形を利用した問題がほとんどなので、\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)が不定形ということを押さえておけばよいと思います。
他にも不定形は全7パターンあるので、詳しく知りたい人は【関数の極限】不定形の全7パーンを分かりやすく解説の記事をチェックしてみましょう。
【講義2】極限が収束するための必要条件
極限が有限の値に収束するために満たすべき条件としては、次の2つを確認することが多いです。
☞有限値への収束が確定
・極限をとった値が不定形となっていること。
☞有限値に収束する可能性あり(必要条件)
1点目はそのままではありますが、極限の計算結果が特定の値になることが確認できれば有限値に収束することが確定します。
2点目は、極限を計算した結果が特定の値にならない場合でも、不定形になっていれば有限値に収束する可能性があります。ただし、注意点としては講義1でも述べた通り、不定形はどんな値になるかが定まっていない状態なので、裏を返せば収束しない可能性もあります。そのため、『不定形になる』という条件を用いて極限の収束を論証する場合は、本当に有限の値に収束するかの確認が必要(端的に言うと十分条件の確認が必要)です。
この2つの条件を使うことで極限値が収束するような未定係数を求めることができますが、具体的な方法については、後続の演習問題の中で確認していきましょう。
【講義3】分母が0の極限が収束するための必要条件
最後に、入試問題で頻出パターンである分母が0となる極限のパターンで、具体的に極限が収束するために満たすべき必要条件を考えてみましょう。
分母が0になるということは純粋に考えると \(\small \displaystyle \frac{■}{0}\)の形になるので、■が1や100や-1000といった値の場合、分母に0があるので無限大に発散してしまいます。しかし、唯一分子が0の場合だけは \(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形となり有限の値に収束する可能性が残ります。
このことから、『(分子)=0』となることが有限の値に収束するための必要条件になります。
ここで注意したいのは、『(分子)=0』はあくまで必要条件なので、不定形であれば必ず有限値に収束するわけではないということです(【講義1】不定形とはでも解説の通り発散する場合もある)。そのため、不定形になる条件を満たす場合に本当に有限値に収束するかを確認する必要があります。詳細は、【問題2】極限が収束するための係数決定の演習問題で解説していきます。
不定形だからといって必ず有限値に収束するわけではないですが、有限値に収束するためには不定形になることが必要条件であると理解しておきましょう。
【問題&解説】極限値を持つような係数決定問題
極限が有限値に収束するための係数決定問題について典型パターンを3問厳選してみました。
(1)等式 \(\small \displaystyle \lim_{x \to \infty} (\sqrt{x^2+ax+5}-\sqrt{x^2-3})=4\)が成り立つような定数\(\small a\)の値を求めよ。
[東京電機大]
(2)極限 \(\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\sqrt{a+\cos x}-b}{(x-\pi)^2}=\frac{1}{4}\)となるように定数\(\small a, b\)を定めよ。
[お茶の水女子大]
(3)極限 \(\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}-(a+bx)}{x^2}\)が有限の値となるように、定数\(\small a,b\)の値を定め、そのときの極限値を求めよ。
[大阪市大]
【問題1】確定値に収束する極限の係数決定(難易度:★☆☆)
(1)等式 \(\small \displaystyle \lim_{x \to \infty} (\sqrt{x^2+ax+5}-\sqrt{x^2-3})=4\)が成り立つような定数\(\small a\)の値を求めよ。
[東京電機大]
・本問では式変形することで極限値が確定値で表せるので『計算結果\(\small =4\)』として係数を求める。
そのまま極限をとっても\(\small \infty – \infty\)の不定形になってしまうので、分母分子に\(\small \sqrt{x^2+ax+5}+\sqrt{x^2-3}\)を乗算することで有理化を行う。
\begin{split}
\small (左辺) &\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x^2+ax+5}-\sqrt{x^2-3})\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} \frac{(\sqrt{x^2+ax+5})^2-(\sqrt{x^2-3})^2}{\sqrt{x^2+ax+5}+\sqrt{x^2-3}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} \frac{ax+8}{\sqrt{x^2+ax+5}+\sqrt{x^2-3}}\\
\end{split}
分母の最高次数で括り出すことで
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \infty} \frac{ax+8}{\sqrt{x^2 \left(1+\dfrac{a}{x}+\dfrac{5}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1-\dfrac{3}{x^2}\right)}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} \frac{\color{#ef5350}x\left(a+\dfrac{8}{x}\right)}{\color{#ef5350}x\sqrt{1+\dfrac{a}{x}+\dfrac{5}{x^2}}+\color{#ef5350}x\sqrt{1-\dfrac{3}{x^2}}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \infty} \frac{a+\dfrac{8}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{a}{x}+\dfrac{5}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x^2}}}\\
&\small \displaystyle =\frac{a+\color{#ef5350}0}{\sqrt{1+\color{#ef5350}0+\color{#ef5350}0}+\sqrt{1-\color{#ef5350}0}}\\
&\small \displaystyle =\frac{a}{2}\\
\end{split}
よって、極限値が\(\small \displaystyle \frac{a}{2}\)に収束したので、この値が右辺の 4 と一致すればよいので
\begin{split}
\small \displaystyle \frac{a}{2} &\small =4\\
\small ∴ \space \color{red}{a}&\small \color{red}{=8 \quad \cdots 【答】}\\
\end{split}
【問題2】極限が収束するための係数決定(難易度:★★☆)
(2)極限 \(\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\sqrt{a+\cos x}-b}{(x-\pi)^2}=\frac{1}{4}\)となるように定数\(\small a, b\)を定めよ。
[お茶の水女子大]
(3)極限 \(\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}-(a+bx)}{x^2}\)が有限の値となるように、定数\(\small a,b\)の値を定め、そのときの極限値を求めよ。
[大阪市大]
⇒詳細は「【講義3】分母が0の極限が収束するための必要条件」を参照。
・(3)は係数決定するための条件式を見つけ出すコツとして、そもそも収束する箇所は有限値になるための条件にはならないので発散する箇所をに着目することがポイント!
左辺について、\(\small x \to \pi\)の極限をとると分母が0、分子が
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \pi} (\sqrt{a+\cos x}-b )\\
&\small \displaystyle =\sqrt{a-1}-b\\
\end{split}
となることから、左辺の極限が有限値に収束するためには\(\small \sqrt{a-1}-b = 0\)(『分子\(\small =0\)』)となることが必要条件となる[*1]。
*1:【補足】なぜ『分子\(\small =0\)』となる必要があるのか?
数学では分母に0が来ることはご法度なので論証には書くことはできないが、上記の論証で言いたいことのイメージが分かりやすくなるようにあえて直接的に表現するならば、そのまま\(\small x \to \pi\)の極限をとると\(\small \displaystyle \frac{\sqrt{a-1}-b}{0}\)となるが、その値は\(\small \sqrt{a-1}-b \neq 0\)の場合\(\small \pm \infty\)に発散し、\(\small \sqrt{a-1}-b = 0\)の場合、\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になることから、発散もしくは有限値に収束する。
一方で右辺の値は \(\small \displaystyle \frac{1}{4}\)であり有限値に収束している。ということは、発散もしくは有限値に収束する\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になる必要があるので、分子が0、すなわち\(\small \sqrt{a-1}-b = 0\)である必要があるワケだ。
ゆえに
\begin{split}
&\small \sqrt{a-1}-b =0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small b =\sqrt{a-1} \space \cdots ①\\
\end{split}
①が不定形になるための必要条件となる。
ここで注意したいのは、①の条件を満たしていれば不定形にはなるが、実際に有限値に収束するかはまだ分からないという点である。そのため、①の条件をもとの問題の左辺に代入することで有限の値に収束するかを確認する必要がある。
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\sqrt{a+\cos x}-b}{(x-\pi)^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{\sqrt{a+\cos x}-\sqrt{a-1}}{(x-\pi)^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{(\sqrt{a+\cos x})^2-(\sqrt{a-1})^2}{(x-\pi)^2(\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1})} \space ◀有理化\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{\cos x +1}{(x-\pi)^2(\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1})}\\
\end{split}
一旦有理化まで行ったがこのままではまだ分母の \(\small x -\pi\)があるため、極限をとると分母が0になってしまう。そこで、分母の\(\small x-\pi\)をうまく処理できないか考える。
経験則として分母が0になる極限の問題で三角関数を含む場合は、
$$\small \lim_{x \to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$
を使って収束する形に式変形するのが王道なので、今回であれば
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\sin (x-\pi)}{x-\pi}=1\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\left(\frac{\sin (x-\pi)}{x-\pi}\right)^2=1\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\sin^2 (x-\pi)}{(x-\pi)^2}=1 \quad \cdots ②\\
\end{split}
の形に式変形していく方針で考えていく。
上記の公式を適用するためには分子の\(\small \cos x +1\)をうまく\(\small \sin x\)と結びつける必要がある。ここでよく利用される公式が半角の公式 [*2]
\begin{split}
&\small \sin^2 \frac{x}{2}= \frac{1-\cos x}{2} \space \\
\end{split}
である。
*2:【補足】半角の公式は暗記不要!?
三角関数に関する公式は数が多いので個人的には半角の公式は2倍角の公式から導出すればよいと思っています。
\begin{split}
&\small \cos 2x = 1-2\sin^2 x\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \sin^2 x= \frac{1-\cos 2x}{2}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \sin^2 \frac{x}{2}= \frac{1-\cos x}{2} \space ◀x \to \frac{x}{2}に置き換え\\
\end{split}
\(\small \displaystyle \cos^2 \frac{x}{2}\)も\(\small \cos 2x = 2\cos^2 x -1\)を利用することで同様に導出可能です。
②の左辺の形に近づけたいので、\(\small \sin x\)の引数を\(\small x \to x-\pi\)に置き換えてあげると
\begin{split}
&\small \sin^2 \frac{x-\pi}{2}= \frac{1-\cos (x-\pi)}{2} \\
\small \Leftrightarrow \space &\small \sin^2 \frac{x-\pi}{2}= \frac{1+\cos x}{2} \space ◀\cos(x-\pi)=-\cos x\\
\small \Leftrightarrow \space &\small 1+\cos x= 2\sin^2 \frac{x-\pi}{2}\\
\end{split}
この結果を有理化した式に代入することで
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to \pi}\frac{\color{#ef5350}{\cos x +1}}{(x-\pi)^2(\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1})}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{\color{#ef5350}{2\sin^2 \dfrac{x-\pi}{2}}}{(x-\pi)^2(\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1})}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{2\sin^2 \dfrac{x-\pi}{2}}{\left(\dfrac{x-\pi}{\color{#ef5350}2}\right)^2\cdot \color{#ef5350}4 \cdot (\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1})}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to \pi}\frac{1}{2}\left(\color{red}{\frac{\sin \dfrac{x-\pi}{2}}{\dfrac{x-\pi}{2}}}\right)^2\cdot \frac{1}{\sqrt{a+\cos x}+\sqrt{a-1}}\\
\end{split}
\(\small x \to \pi\)の極限をとると赤字箇所は無事1に収束するので、
\begin{split}
&\small \displaystyle \frac{1}{2}\cdot \color{red}{1}^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{a+\cos \pi }+\sqrt{a-1}}\\
&\small \displaystyle =\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{a-1 }+\sqrt{a-1}}\\
&\small \displaystyle =\frac{1}{4\sqrt{a-1 }}\\
\end{split}
上記の値が\(\small \displaystyle \frac{1}{4}\)と一致すればよいので
\begin{split}
&\small \displaystyle \frac{1}{4\sqrt{a-1 }}=\frac{1}{4}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \sqrt{a-1}=1\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle a-1=1 \space ◀両辺を2乗\\
\small ∴ \space &\small \displaystyle a=2\\
\end{split}
得られた解は、\(\small \sqrt{a-1}\)のルートの中身が0以上(負にならない)条件である\(\small a≧1\)を満たすため適切。\(\small b\)の値は①の関係式から、\(\small b=\sqrt{a-1}=\sqrt{2-1}=1\)。
よって、\(\small a=2, \space b=1\)…【答】.
\(\small x \to 0\)の極限をとると分母は0、分子は
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}-(a+bx)\}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\{\sqrt{9-0+7\cdot 1}-a\}\\
&\small \displaystyle =4-a\\
\end{split}
となる。ここで、分子が\(\small 4-a \neq 0\)の場合、\(\small \infty\)または\(\small -\infty\)に発散、\(\small 4-a = 0\)の場合、\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形になるので発散もしくは有限の値に収束する。
今回の問題では、極限が有限の値に収束する場合を考えているので、『(分子)\(\small =0\)』、すなわち
\begin{split}
&\small 4-a = 0\\
&\small ∴ \space \color{red}{a= 4 \space \cdots ①}\\
\end{split}
①の結果を問題の式に代入して極限を計算すると
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}-(4+bx)}{x^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{(9-8x+7\cos 2x)-(4+bx)^2}{x^2\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4+bx)\}} \space ◀有理化\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-8(1+b)x-b^2x^2}{x^2\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4+bx)\}}\quad \cdots ②\\
\end{split}
ここで分母の\(\small \sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4+bx)\)の部分については、\(\small x \to 0\)の極限で
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}(\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4+bx))\\
&\small \displaystyle =\sqrt{9+7\cdot 1}+(4+0)\\
&\small \displaystyle =\sqrt{16}+4\\
&\small \displaystyle =8\\
\end{split}
となり有限値であることから、残りの
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-8(1+b)x-b^2x^2}{x^2}\\
\end{split}
の部分が有限値に収束すればよいことになる。この極限が発散してしまう原因は分母に\(\small x^2\)が残ってしまうことが原因なので、分母の\(\small x^2\)をうまく処理できない項を見つけ出すことがポイントになる。
そこで上記の式を、もう少し分解して見てみると
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-8(1+b)x-b^2x^2}{x^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\left[\frac{7(\cos 2x -1)}{x^2}-\frac{8(1+b)}{x}-b^2\right] \\
\end{split}
となる(分子の定数項、\(\small x\)の項、\(\small x^2\)の項のイメージで分類)。すると、第3項目は明らかに\(\small -b^2\)に収束しているので発散しない。また、第1項目についても
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{7(\cos 2x -1)}{x^2}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{7\color{#ef5350}{(\cos 2x -1)}}{x^2}\cdot\frac{\color{#ef5350}{\cos 2x +1}}{\cos 2x +1}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{7\color{#ef5350}{(\cos^2 2x -1^2)}}{x^2(\cos 2x +1)}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{-7\sin^2 2x}{x^2(\cos 2x +1)}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{-7}{\cos 2x +1}\left(\frac{\sin 2x}{x}\right)^2\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{-7\cdot \color{#ef5350}4}{\cos 2x +1}\left(\frac{\sin 2x}{\color{#ef5350}2x}\right)^2\\
&\small \displaystyle =-\frac{28}{1 +1}\cdot1^2\\
&\small \displaystyle =-14\\
\end{split}
となり収束する。残りの第2項目については、
\begin{split}
&\small \lim_{x \to 0}\frac{8(1+b)}{x}=\frac{8(1+b)}{0}
\end{split}
となるので、分子の\(\small 8(1+b)\)が0でない場合は発散してしまう。そのため、『(分子)\(\small =0\)』すなわち、\(\small 8(1+b)=0\)とすることで\(\small \displaystyle \frac{0}{0}\)の不定形に持ち込むことが有限値に収束するための必要条件となる。
よって、この条件を満たす\(\small b\)の値は、\(\small b=-1\)…③と求まる。
あとは、③の条件を②に代入して実際に有限の値に収束することを確認していく。
\begin{split}
&\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-8(1+\color{#ef5350}b)x-\color{#ef5350}b^2x^2}{x^2\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4+\color{#ef5350}bx)\}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-8(1+\color{#ef5350}{(-1)})x-\color{#ef5350}{(-1)}^2\cdot x^2}{x^2\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4\color{#ef5350}-x)\}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\frac{7\cos 2x -7-x^2}{x^2\{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4-x)\}}\\
&\small \displaystyle =\lim_{x \to 0}\left[\frac{7(\cos 2x -1)}{x^2}-1\right]\\
&\small \displaystyle \quad \times \frac{1}{\sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4-x)}\\
\end{split}
ここで\(\small \displaystyle \lim_{x \to 0}\frac{7(\cos 2x -1)}{x^2}\)の極限は先程確認した通り-14に収束し、分母の\(\small \sqrt{9-8x+7\cos 2x}+(4-x)\)も\(\small x \to 0\)で8に収束することから、式全体としては
\begin{split}
\small (与式) &\small \displaystyle =(-14-1)\times \frac{1}{8}\\
&\small \displaystyle =-\frac{15}{8}\\
\end{split}
よって、\(\small a=4, \space b=-1\)のとき極限が有限値に収束し、その値は\(\small \displaystyle -\frac{15}{8}\)…【答】.
本記事のまとめ
今回は極限が有限の値に収束するための必要条件について解説してみました。不定形の性質をうまく利用して収束するための条件を絞り込んでいく解き方は、はじめは難しく感じるかもしれませんが本記事で解説したポイントを押さえれば、ほとんどの問題は解けるようになると思います。
最後に本記事のポイントをおさらいして終わりにしましょう。
☆重要ポイント☆
≫極限が収束するためには?
・極限を計算したら有限値になる(発散しない)
・極限を計算したら不定形になる(有限値になる可能性あり、確定ではない)
<頻出パターン>
・分母が0になる場合は『分子\(\small =0\)』が必要条件
今回は以上です。お疲れさまでした!
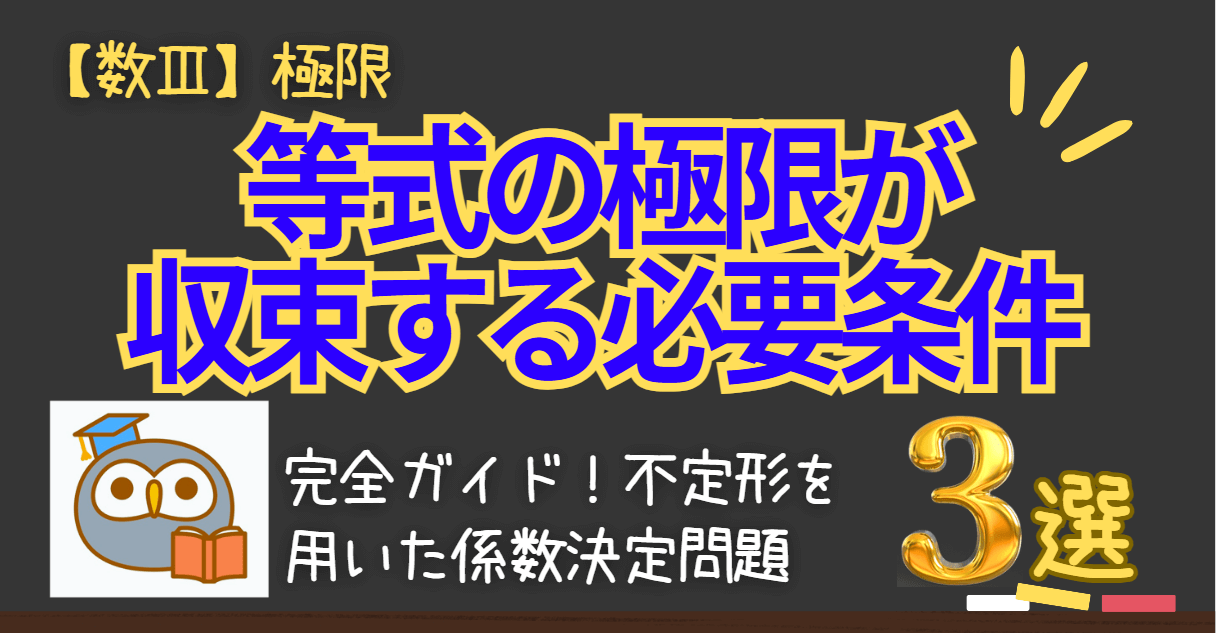
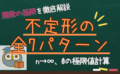
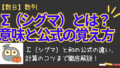
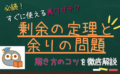


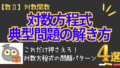
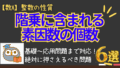
コメント