平方完成って、なんだかややこしい…そう感じていませんか?
たとえば、「\(\small x^2+6x+5\)」のような式を見ても、どう変形していけばいいのか迷う人も多いでしょう。
この記事では、平方完成の意味から裏ワザ的手順までを、「なぜそうするのか」が分かるように丁寧に解説します!
平方完成は、2次関数のグラフ・最大最小・解の公式など、高校数学のあらゆる場面で登場します。ここでしっかり理解しておけば、このあとの単元がグッと楽になるので、一緒に苦手を克服していきましょう!
- 平方完成のやり方が分からない・覚えられない
- 計算ミスばかりしてしまう
- 「なぜこの形にするのか」を理解したい
- 平方完成の裏ワザを知りたい
【基礎講義】平方完成のやり方
【講義1】平方完成とは
2次式とは簡単にいえば『\(\small ▲x^2+●x+■\)』のような式のことです。最高次数が2乗であることから2次式と言われています。
たとえば、\(\small x^2+6x+5\)という2次式があった場合、この式は、
\begin{split}
&\small x^2+6x+5 = (x+3)^2-4
\end{split}
のように式変形できます(右辺を展開すると左辺になることが分かると思います)。
このように、『\(\small ▲(x+●)^2+■\)』の形に式変形することを平方完成というわけです。でも、どうやって\(\small (x+3)^2-4\)の形に平方完成するのか?については、【講義3】平方完成のやり方【3ステップ】で解説します。
【講義2】なぜ平方完成するのか
突然ですが、\(\small y=2x+1\)がどんなグラフか想像してみてください。これは1次関数なので、傾きが2、切片が1の右肩上がりのグラフだということがすぐイメージできたでしょう。
では、\(\small y=x^2+2x+4\)はどんなグラフでしょうか?今度は、すぐにはグラフをイメージできなかったのではないでしょうか?\(\small x^2\)の係数が正なので下に凸の放物線、切片が4ということくらいは直ぐ分かりますが、2次関数で重要な点である頂点の座標は\(\small y=x^2+2x+4\)の形を見ただけではすぐには分かりません。
このように、2次関数は一般に\(\small y=ax^2+bx+c\)の形で表されるわけですが、この形は2次関数の頂点の座標がすぐには分かりにくい形なわけです。
では、頂点の座標を知りたい場合、どのような形になっていればすぐ分かるでしょうか?答えは、\(\small y= a(x-p)^2+q\)の形になっていれば、点\(\small (p,q)\)が頂点の座標になるのでした。
【補足】\(\small y=a(x-p)^2+q\)の頂点が点\(\small (p,q)\)になる理由
\(\small y=ax^2\)は原点を頂点とする放物線でした。この関数を\(\small x\)軸方向に\(\small p\)、\(\small y\)軸方向に\(\small q\)だけ平行移動すると頂点の座標は原点\(\small (0,0)\) ⇒ \(\small (p,q)\)に移動します。そしてこの時の2次関数の式は、\(\small x\)⇒\(\small x-p\)、\(\small y\)⇒\(\small y-q\)に置き換えてあげればよかったので
\begin{split}
&\small \color{#ef5350}{y-q}=a\color{#ef5350}{(x-p)}^2\\
\small \Leftrightarrow \space &\small y= a(x-p)^2+q\\
\end{split}
になることが分かります。
平行移動の考え方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も併せて確認しておきましょう!
【2次関数】平行移動した式を求める公式(なぜマイナスになるのか分かりやすく解説)
つまり、2次関数のグラフの概形を把握するうえで最も重要な点である頂点の座標を知るためには
\(\small y=ax^2+bx+c\)の形を\(\small y= a(x-p)^2+q\)の形に変形してあげる必要があるわけです。
この変形は2次関数を『\(\small ▲(x+●)^2+■\)』の形に式変形するという平方完成に他なりません。
このように、平方完成は2次関数のグラフの概形(頂点の座標)を把握するために必要な式変形になるわけです。
【講義3】平方完成のやり方【3ステップ】
では平方完成の使いどころもわかったところで、いよいよ平方完成のやり方について解説!どんな2次関数であっても、これから紹介するたったの3ステップを順番通りに行うだけで簡単に平方完成ができます。
・STEP2:括弧内を\(\small \displaystyle x+\frac{b}{2a}\)とする
・STEP3:括弧を展開して元の式との差を調整
一般的な平方完成の手順って、\(\small x^2\)の係数で括って、\(\small x\)の係数を2で割って、括弧の2乗の形を作るために足したり引いたり…、という具合に、複雑で頭がパンクしちゃいそうですよね。
でも上記の3STEPは、そのような面倒なことをしなくてもちょっとした暗記をするだけで簡単にかつ検算もできてしまう方法なので、是非手順を覚えて使ってみてください!
では、具体的な例題を通してステップを確認していきましょう!
\(\small 2x^2-12x-3\)を平方完成せよ。
平方完成の際は、『\(\small ▲(x+●)^2+■\)』の形をしっかり意識しましょう。
\(\small x^2\)の係数は「\(\small 2\)」なので、今回の場合は
\begin{split}
&\small \color{#ef5350}{2(x+●)^2}+■
\end{split}
のように平方完成の『\(\small (\quad)^2\)』の係数を\(\small 2\)としておきます。
\(\small a\)や\(\small b\)は\(\small ax^2+bx+c\)の各係数の値になります。\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}\)の形が少し複雑ですが、2次関数で頻出の軸の\(\small x\)座標が\(\small \displaystyle x=-\frac{b}{2a}\)であることを覚えていれば、『\(\small \displaystyle x-\) [軸の\(\small x\)座標]』と覚えてもらっても大丈夫です。
というわけで、\(\small (\quad)^2\)の中身は、\(\small a=2\), \(\small b=-12\)なので、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=-3\)となることから、括弧内を\(\small x-3\)にしてあげればよいので、STEP1と合わせると
\begin{split}
&\small 2\color{#ef5350}{(x-3)^2}+■
\end{split}
となります。
STEP2までできたら最後は『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開して元の式 \(\small 2x^2-12x-3\)と比較することで、過剰(もしくは過小)な分を『■』の数字で帳尻合わせする作業になります。
ではまずはSTEP2で作った『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small 2\color{#ef5350}{(x-3)^2} &\small =2(x^2-6x+9)\\
&\small =\color{blue}{2x^2-12x}+18\\
\end{split}
このとき、最初の2項(青字部分)は必ず元の式と一致します。正確に言えば、最初の2項が一致するようにSTEP1やSTEP2で\(\small x^2\)の係数を\(\small (\quad)^2\)の前に持ってきたり、括弧内を\(\small \displaystyle x+\frac{b}{2a}\)のような形にしていたわけです(なぜこの形にすれば一致するのかの解説はこちらへ)。
なので、もし展開したときに\(\small x^2\)や\(\small x\)の係数が元の式と一致しない場合は、どこかが間違っているということなので、STEP1やSTEP2に誤りがないか再確認をしましょう(ここで検算もできて一石二鳥!)。
というわけで、話をもとに戻すと、展開したときに元の式と数字部分(定数項)にズレがある場合は、ズレている分を『■』に設定してあげれば平方完成は終了です。
今回であれば、
展開した式:\(\small 2x^2-12x \color{#ef5350}{+18}\)
元の式 :\(\small 2x^2-12x \color{#ef5350}{-3}\)
なので、展開した式の『\(\small +18\)』が元の式の『\(\small -3\)』にならないといけないので、\(\small -18\)をしてから\(\small 3\)を足せば元の式になります。
\begin{split}
&\small 2x^2-12x +18\color{#ef5350}{-18+3}\\
&\small =2x^2-12x +18\color{#ef5350}{-21}\\
\end{split}
第1~3項目の\(\small 2x^2-12x +18\)部分は、STEP2で『\(\small ( \quad)^2\)』に式変形した通り \(\small 2(x-3)^2\)であることに注意すると、
\begin{split}
&\small 2x^2-12x +18\color{#ef5350}{-21}\\
&\small =2(x-3)^2 \color{#ef5350}{-21}\\
\end{split}
この式は、我々が目指していた『\(\small ▲(x+●)^2+■\)』の形ですから、これで平方完成完了です!
よって、平方完成した式は \(\small2(x-3)^2-21\)…【答】となります。
【補足】STEP1・STEP2の意味
実際に2次式の一般形 \(\small ax^2+bx+c\)を平方完成してみると
\begin{split}
\small ax^2+bx+c &\small =a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c\\
&\small =a\left(x^2+\color{#ef5350}2\cdot \frac{b}{\color{#ef5350}2a}x+\color{#5c6bc0}{\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}}\right)+c\\
&\small =a\left\{ \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}\right\}+c\\
&\small =a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c\\
&\small =a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}\\
\end{split}
となります。この式を見ると、STEP1・STEP2に出てきた通り『\(\small (\quad)^2\)』の係数に\(\small x^2\)の係数である\(\small a\)がきて、『\(\small (\quad)^2\)』の中身が\(\small \displaystyle x+\frac{b}{2a}\)になっていることが分かります。
最後の定数項 \(\small \displaystyle -\frac{b^2-4ac}{4a}\)の部分も暗記してしまえば公式に代入するだけですが、個人的には大変ですし、覚えてもあまり使う頻度は高くない(一時的には覚えられても時間が経つと忘れてしまう暗記はしたくない…)ので、STEP3のように最後にちょこっと帳尻合わせするって覚えておく方が簡単かなと思います。
【講義4】平方完成をするときの注意点
平方完成をするときによくミスしがちなポイントと対策をまとめました。テストの見直しのときはこれらのことに注意すると点数アップできるかも!?
・STEP1を忘れない!
☞ \(\small x^2\)の係数が1のことが多いので意外と忘れがち…
・STEP3の展開は一つずつ丁寧に!
☞ 特に『\(\small (\quad)^2\)』の前に係数がある場合は、まず『\(\small (\quad)^2\)』内の展開をしてから括弧を外そう(一気にやると計算ミスのもと!)
●対策
・平方完成が終わったら必ず検算(見直しのときに検算でもOK)
☞ 平方完成した式を展開したら元の式になるかを確認しよう
・時間がなければ、\(\small x = 0\)を代入して定数項が一致することを確認するだけでも効果あり!
対策の2つ目は、展開した式と元の式の両方に同じ\(\small x\)の値を代入したら一致するはずなので、計算が簡単な\(\small x=0\)を代入することで確認してみるという検算方法です。
例えば講義3の例題で試しに確認してみると、平方完成した式 \(\small 2(x-3)^2-21\)に\(\small x=0\)を代入すると、\(\small 2\cdot (-3)^2-21=18-21=-3\)となり、元の式 \(\small 2x^2-12x-3\)の定数項 \(\small -3\)と一致することが分かります(「元の式に\(\small x=0\)を代入する」=「定数項だけが残る」ので、定数項を見ればOK!)。
注意点として、2つ目の検算方法はあくまで簡易的な方法なので、一致したからと言って平方完成した式が必ずあっているとは限りません。例題3であれば、たとえば、\(\small 2(x\color{red}{+3})^2-21\)のように±の符号が間違っていても\(\small x=0\)を代入した値は一致してしまいます。
なので、しっかり確認したいのであれば1つ目の展開して検算する方法で確認しましょう。
【問題&解説】平方完成の問題
では実際の問題を通して平方完成のやり方を確認していきましょう。慣れてきたら
【問題1】平方完成(基本形)
\(\small x^2+4x+5\)を平方完成せよ。
\(\small x^2\)の係数が1で、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=2\)(∵ \(\small a=1\),\(\small b=4\))なので、まずは
$$\small \color{#ef5350}{(x+2)^2}+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
&\small (x+2)^2 =x^2+4x\color{#ef5350}{+4}\\
\end{split}
なので、問題の式 \(\small x^2+4x+5\)と一致させるためには、定数項部分が\(\small +1\)されていればOK(\(\small x^2+4x+4\color{#ef5350}{+1}=x^2+4x+5\)となり一致する)なので、\(\small (x+2)^2+1\)…【答】.
【補足】
答の式を展開すると、
\begin{split}
\small (x+2)^2+1 &\small =(x^2+4x+4)+1\\
&\small =x^2+4x+5\\
\end{split}
となり、問題の式と一致するので答えがあっていることが簡単に検算できます!
【問題2】平方完成(a≠1型)
\(\small 3x^2-18x+14\)を平方完成せよ。
\(\small a= 3\)、\(\small b= -18\)より、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=-3\)なので
$$\small \color{#ef5350}{3}(x\color{#ef5350}{-3})^2+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small 3(x-3)^2 &\small =3(x^2-6x+9) \quad ◀丁寧に展開\\
&\small =3x^2-18x\color{#ef5350}{+27}\\
\end{split}
※ちなみに、第1,2項目が\(\small 3x^3-18x\)になっていて問題の第1,2項目とも一致しているので、ここまでは合っていることが検算できます。
最後に問題の式の定数項『\(\small 14\)』と比較して、上記で展開した式の定数項が『\(\small 27\)』になっているので、\(\small -13\)することで、\(\small 27-13=14\)になるように調整します。
よって、\(\small 3(x-3)^2-13\)…【答】.
【問題3】平方完成(分数あり)
\(\small 2x^2+6x-2\)を平方完成せよ。
\(\small a=2\)、\(\small b=6\)より、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=\frac{3}{2}\)なので、
$$\small \color{#ef5350}{2}\left(x\color{#ef5350}{+\frac{3}{2}}\right)^2+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small 2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 &\small =2\left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right) \\
&\small =2x^2+6x+\frac{9}{2}\\
\end{split}
最後は定数項部分の帳尻合わせをすれば完成ですが、分数だと少し考えにくいかもしれません。
なので、シンプルに展開した式の定数項 \(\small \displaystyle \frac{9}{2}\)を引き算して、\(\small -2\)を加えることで元の式の形にしてあげるのが一番考えやすいでしょう。
すなわち
\begin{split}
&\small \color{#5c6bc0}{2x^2+6x+\frac{9}{2}} \color{#ef5350}{-\frac{9}{2}-2} \quad [*1]\\
&\small =2x^2+6x+\frac{9}{2} \color{#ef5350}{-\frac{13}{2}}\\
\end{split}
*1:【補足】式変形の解説
青色部分が\(\small \displaystyle 2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 \)の部分です。
赤色部分が元の式にするための調整部分になっており、定数項の \(\small \displaystyle \frac{9}{2}\)が邪魔なので引き算して、元の問題の定数項である\(\small -2\)を加えています。
\begin{split}
&\small \color{#5c6bc0}{2x^2+6x+\frac{9}{2}} \color{#ef5350}{-\frac{9}{2}-2}=2x^2+6x-2\\
\end{split}
この考え方は、分数の場合でなくても使えます!
よって、平方完成した式は、\(\small \displaystyle 2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{13}{2}\)…【答】.
【問題4】平方完成(aがマイナス)
\(\small -x^2+4x+3\)を平方完成せよ。
\(\small a=-1\)、\(\small b=4\)より、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=-2\)なので、
$$\small \color{#ef5350}{-}(x\color{#ef5350}{-2})^2+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small -(x-2)^2 &\small =-(x^2-4x+4) \\
&\small =-x^2+4x\color{#ef5350}{-4}\\
\end{split}
最後に定数項部分を元の式の『\(\small 3\)』に合わせるために、
\begin{split}
&\small -x^2+4x-4\color{#ef5350}{+4+3}\\
&\small =-x^2+4x-4\color{#ef5350}{+7}\\
\end{split}
としてあげればよいので、平方完成した式は、\(\small -(x-2)^2+7\)…【答】.
※最後の定数項の調整は、\(\small -4\)に\(\small +7\)したら元の式の定数項 \(\small +3\)になると考えてもOKです。
【問題5】平方完成(特殊形)
次の2次式を平方完成せよ。
(1)\(\small x^2-8x\)
(2)\(\small \displaystyle \frac{1}{2}x^2+3x-1\)
定数項が0のパターン。解き方自体はこれまでと同じです。
\(\small a=1\)、\(\small b=-8\)より、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=-4\)なので、
$$\small (x\color{#ef5350}{-4})^2+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small (x-4)^2 &\small =x^2-8x\color{#ef5350}{+16}\\
\end{split}
最後に定数項を0にするためには、
\begin{split}
\small x^2-8x+16\color{#ef5350}{-16}\\
\end{split}
のように展開した式から\(\small -16\)をすればよいので、平方完成した式は、\(\small (x-4)^2-16\)…【答】.
\(\small x^2\)の係数が分数のパターンです。計算ミスに注意して平方完成していきましょう!
\(\small \displaystyle a=\frac{1}{2}\)、\(\small b=3\)より、\(\small \displaystyle \frac{b}{2a}=\frac{3}{2\cdot \dfrac{1}{2}}=3\)なので、
$$\small \displaystyle \color{#ef5350}{\frac{1}{2}}(x\color{#ef5350}{+3})^2+■$$
の形に変形。『\(\small (\quad)^2\)』部分を展開すると
\begin{split}
\small \displaystyle \frac{1}{2}(x+3)^2 &\small =\frac{1}{2}\left(x^2+6x+9\right)\\
&\small =\frac{1}{2}x^2+3x+\color{#ef5350}{\frac{9}{2}}\\
\end{split}
定数項部分を\(\small \displaystyle -\frac{9}{2}\)してから元の式の定数項である\(\small -1\)すれば元の式に一致することから、
\begin{split}
&\small \frac{1}{2}x^2+3x+\frac{9}{2}\color{#ef5350}{-\frac{9}{2}-1}\\
&\small =\frac{1}{2}x^2+3x+\frac{9}{2}\color{#ef5350}{-\frac{11}{2}}\\
\end{split}
よって、平方完成した式は、\(\small \displaystyle \frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2}\)…【答】.
本記事のまとめ
今回は平方完成の裏ワザを紹介しましたがいかがでしたか?平方完成は2次関数のグラフをかく問題や最大値、最小値を求める問題など受験でも必須の分野の基礎となる式変形になるので、今回紹介した裏ワザ的平方完成術も参考にして正確かつ素早くできるようにしっかり練習を積み重ねておきましょう!
では今回は以上です。お疲れさまでした!
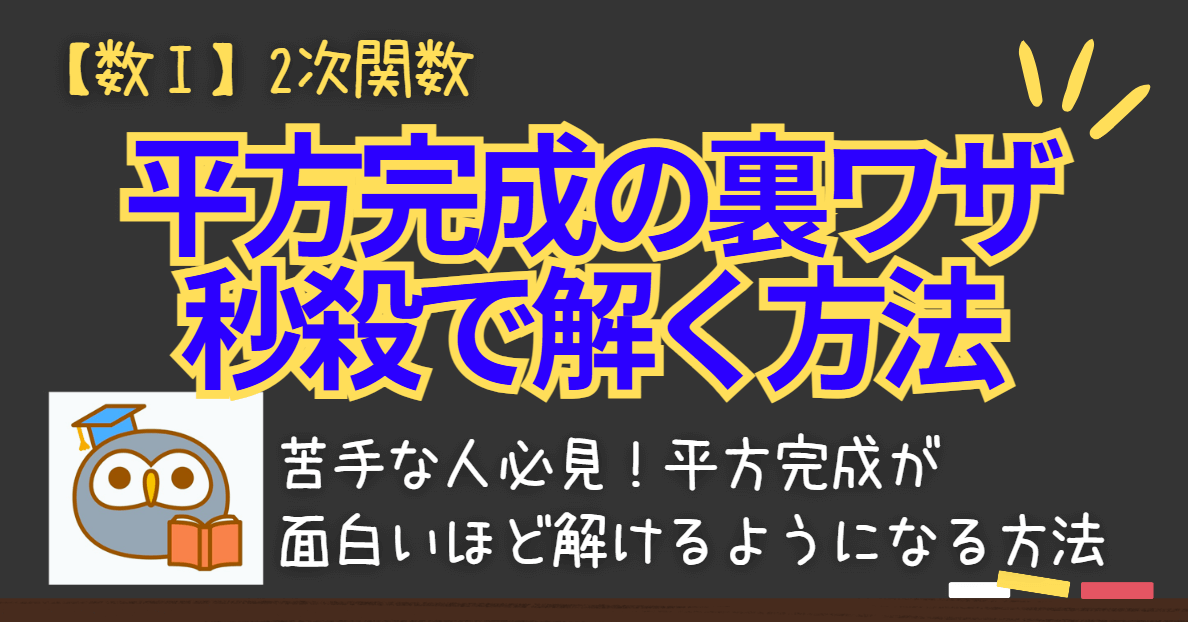
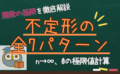
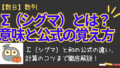
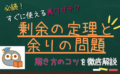


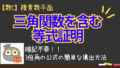
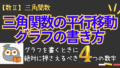
コメント