今回は対数を含む方程式の典型問題の解き方を徹底解説していきます。
対数方程式を解く過程には様々な落とし穴が存在します。真数条件の確認だったり、対数の底が一致しているかの確認だったり、底が満たすべき条件の確認だったり…、問題を解くときにいつも何かしらの確認を忘れがちですよね(^^;)。また、対数方程式の解き方自体も対数の中身を比較して解く方法や\(\small \log\)自体を文字で置換して2次方程式を解く方法など複数の解法があり見極めも必要です。
そこで本記事では対数方程式を解くときに気を付けるべき注意点と典型的な問題パターンを分かりやすく解説していきます。今回扱う問題の解き方・考え方をしっかりマスターして対数方程式の苦手を克服しましょう!
- 対数方程式の典型問題パターンと解き方のコツを知りたい人
- 対数方程式を解く際の注意点を知りたい人
- 大学入試対策、定期テスト対策がしたい人
【基礎講義】対数方程式の代表的な解き方2選
典型的な対数方程式を解く方法は大きく2パターンに集約されます。まずはその代表的な2パターンの解説をしていきます。
【講義1】[解き方①]底を揃えて中身比較
最初の解法は両辺の対数の底を統一し中身を比較する解法です。
この解き方は直感的にも理解しやすいと思いますが、隠れた条件である『真数条件』や『底の条件』に注意が必要です(結構忘れがち…)。
≫真数条件とは?
・真数(\(\small \log\)の中身)が常に正になるという条件のこと。
\(\small \log_a x\)であれば、\(\small x > 0\)が成り立つ。
≫底の条件とは?
・底は常に正かつ1以外になるという条件のこと。
\(\small \log_a x\)であれば、\(\small a > 0\)かつ\(\small a \neq 1\)が成り立つ。
底を揃えて中身を比較する解法では、以下のステップに沿って解いていけばOKです。
・STEP2:両辺の底を揃える
・STEP3:対数の中身をイコールにして方程式を解く
・STEP4:求めた解がSTEP1の条件を満たすか確認する(解の吟味)
真数条件や底の条件は忘れないように、一番はじめに確認しておくのがおすすめです。
【講義2】[解き方②]対数を文字で置換する解法
もう一つの代表的な解法は\(\small \log_a x\)を丸ごと文字でおく解法です。
方程式の中に\(\small (\log_a x)^2\)が含まれている場合など、\(\small \log_a A+\log_a B=\log_a(AB)\)の公式を用いて\(\small \log\)を1つにまとめられない場合は\(\small \log\)自体を文字でおいて方程式の問題に帰着させて解くのが効果的です。
・STEP2:logを丸ごと文字で置換する
・STEP3:置き換えた文字が満たす方程式を解く
・STEP4:求めた解がSTEP1の条件を満たすか確認する(解の吟味)
具体的にどんな場合に利用できるかは実際の問題を解く中で掴んでいきましょう!
↓該当する問題はこちら
【パターン③】置き換えを利用した対数方程式(難易度:★☆☆)
【問題&解説】対数方程式_問題パターン別解説
次の方程式を解け。
(1)\(\small \log_2(x^2+2x)=\log_2(3x+6)\)
(2)\(\small \log_2(x+2)=\log_4(5x+16)\)
(3)\(\small \log_2(x^2-x-18)+\log_2(x-1)=3\)
(4)\(\small (\log_{5}x)^2+2\log_5 x =3\)
(5)\(\small \log_2 x-3\log_x 2=6\)
[(2)駒澤大,(3)千葉工大 類]
↓↓各問題の解説はこちら
(1)次の連立方程式を解け。
\begin{cases}
\small \displaystyle \log_y x +\log_x y=\frac{5}{2}\\
\small \displaystyle \log x +\log y=\log 27\\
\end{cases}
(2)\(\small 8^{x\log_2 x}=x\sqrt{x}\)
↓↓各問題の解説はこちら
【パターン①】底が同じである対数方程式(難易度:★☆☆)
(1)\(\small \log_2(x^2+2x)=\log_2(3x+6)\)を解け。
☞ 『\(\small \color{#ef5350}{\log_{a}} ■ = \color{#ef5350}{\log_a} ●\) ⇔ \(\small ■ = ●\)』が成り立つ。
・求めた解が真数条件を満たすことの確認も忘れずに!
☞ 対数は、必ず『(真数)\(\small > 0\)』を満たす(真数条件)。
・解き方は、【講義1】[解き方①]底を揃えて中身比較を参照。
対数方程式を解き始める前に、まずは対数の中身が満たすべき条件を確認しておこう。
真数条件より、対数の中身は正になることから、\(\small x\)は
\begin{split}
&\small x^2+x >0 ,\space かつ \space 3x+6 > 0\\
\end{split}
の条件を満たす。
これらの不等式を解くと
\begin{split}
&\small x^2+x >0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x(x+1) >0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x<-1, \space 0<x \space \cdots ①\\
\end{split}
\begin{split}
&\small 3x+6>0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small 3x>-6\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x>-2 \space \cdots ②\\
\end{split}
①、②の共通範囲を求める [*1]ことで、\(\small -2< x <-1, \space 0<x\)…③。
*1:【補足】共通範囲をとる理由
冒頭で真数条件から『①かつ②』を満たす、つまり①と②を共に満たす必要があることから共通の範囲を考えることに注意。逆にどちらか一方だけ満たせばよい場合は合計範囲を考えることになる。
両辺の底が同じであることこから、対数の中身も同じになるので
\begin{split}
&\small x^2+x = 3x+6\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x^2-x-6=0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (x-3)(x+2)=0\\
\small ∴ \space &\small x=-2, \space 3\\
\end{split}
求めた解のうち、③の条件を満たすのは \(\small x=3\)…【答】.
最後に求めた解が真数条件を満たすことの確認(解の吟味)も忘れずに!
【パターン②】異なる底を含む対数方程式(難易度:★★☆)
次の方程式を解け。
(2)\(\small \log_2(x+2)=\log_4(5x+16)\)
(3)\(\small \log_2(x^2-x-18)+\log_2(x-1)=3\)
[(2)駒澤大,(3)千葉工大 類]
・異なる底を含む対数方程式では、底の変換公式を利用して底を統一せよ!
底の変換公式
底を\(\small a\) ⇒ \(\small c\)に変更したい場合
$$\small \displaystyle \log_\color{blue}a \color{red}b =\frac{\log_\color{magenta}c \color{red}b}{\log_\color{magenta}c \color{blue}a}$$
定数の\(\small log \)変換
定数を\(\small \log\)表示するには
$$\small k = k \log _a a= \log_a a^k$$
で置き換える。
まずは真数条件より、\(\small x+2>0\) かつ \(\small 5x+16 >0\)を満たす必要があるので
\begin{split}
&\small x+2 > 0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x>-2 \space \cdots ①\\
&\small 5x+16 > 0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle x>-\frac{16}{5} \space \cdots ②\\
\end{split}
①、②の共通範囲より\(\small x >-2\)…③。
次に、底が\(\small \log_2\)と\(\small \log_4\)で異なるため、底を\(\small \log_2\)に統一 [*1]して解く。
*1:【補足】底が異なるときはどの底に揃える?
底を揃える場合は、基本的には小さい値で統一すればOK。
※分数の場合は整数で揃える
例:\(\small \log_3\)と\(\small \log_{\frac{1}{3}}\)であれば、\(\small \log_3\)で統一
\begin{split}
\small \log_4(5x+16) &\small \displaystyle =\frac{\log_2(5x+16)}{\log_2 4}\\
&\small \displaystyle =\frac{1}{2}\log_2(5x+16)\\
&\small \displaystyle =\log_2\sqrt{5x+16}\\
\end{split}
よって、問題の対数方程式は
\begin{split}
&\small \displaystyle \log_2(x+2)=\log_2\sqrt{5x+16}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle x+2 = \sqrt{5x+16} \quad ◀対数の中身が等しい\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle (x+2)^2 = 5x+16\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle x^2-x-12=0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle (x+3)(x-4)=0\\
\small ∴ \space &\small \displaystyle x=-3, \space 4\\
\end{split}
最後に求めた解のうち真数条件③を満たす解は\(\small x=4\)…【答】.
真数条件より、\(\small x^2-x-18 >0\) かつ \(\small x-1 >0\)を満たす必要がある [*1]ので
\begin{split}
&\small x^2-x-18 > 0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x < \frac{1 – \sqrt{73}}{2} ,\frac{1 + \sqrt{73}}{2} < x\space \cdots ①\\
&\small x-1 > 0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle x>1 \space \cdots ②\\
\end{split}
*1:【補足】真数条件は個々の\(\small \log\)で確認
問題の方程式左辺を、
\begin{split}
&\small \log_2(x^2-x-18)+\log_2(x-1)\\
&\small =\log_2(x^2-x-18)(x-1)
\end{split}
に変形してから、真数条件より、\(\small (x^2-x-18)(x-1)>0\)としてしまうのはNG。なぜならば\(\small (x^2-x-18)(x-1)>0\) の解は 『\(\small x^2-x-18>0\)かつ\(\small x-1>0\)』または『 \(\small x^2-x-18<0\)かつ\(\small x-1<0\)』となるが、後者の条件では\(\small \log_2(x^2-x-18)\)や\(\small \log_2(x-1)\)の個々の\(\small \log\)で見ると真数が負になってしまうからである。
なので、真数条件を確認するときには、個々の\(\small \log\)の真数が正という条件で確認する必要がある。
①、②の共通範囲は \(\small \displaystyle \frac{1 + \sqrt{73}}{2} < x\)…③ [*2].
*2:【補足】1と\(\small \displaystyle \frac{1 + \sqrt{73}}{2}\)の大小関係
\(\small 8^2=64\)、\(\small 9^2 =81\)より
\begin{split}
&\small \displaystyle 64<73<81\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle 8<\sqrt{73}<9\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle 9<1+\sqrt{73}<10\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \frac{9}{2}<\frac{1+\sqrt{73}}{2}<5\\
\end{split}
であることから、\(\small \displaystyle 1 < \frac{1+\sqrt{73}}{2}\)であることが分かる。
問題の対数方程式は右辺だけ定数が含まれているので、全体に合わせて\(\small \log_2\)を底とする対数に統一すると、
\begin{split}
&\small \log_2(x^2-x-18)+\log_2(x-1)=3\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_2(x^2-x-18)+\log_2(x-1)=3\color{#ef5350}{\log_2 2}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_2(x^2-x-18)(x-1)=\log_2 2^3\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_2\color{#ef5350}{(x^2-x-18)(x-1)}=\log_2 \color{#ef5350}8\\
\end{split}
左辺と右辺で底が統一できたので対数の中身(赤字部分)が等しくなることから
\begin{split}
&\small (x^2-x-18)(x-1)=8\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x^3-2x^2-17x+18=8\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x^3-2x^2-17x+10=0\\
\end{split}
あとは上記の3次方程式を解いていけばOK(3次方程式の解き方や素早く解く裏ワザは「【3次方程式】裏ワザあり!?因数分解、因数定理、組立除法、係数比較を用いた解法のコツ」を参照してね)。
一般的に有理数解になるように問題が作られているはずなので(メタ読みも大事)、有理数解の候補である \(\small x = \pm 1,\pm2,\pm5,\pm10\)から確認 [*3]していくと、\(\small x=5\)で左辺が0になることが分かる。
*3:【補足】有理数解の候補の絞り込み方
3次方程式の有理数解の候補は、\(\small \displaystyle \color{#ef5350}{\pm \frac{\mathsf{定数項の約数のどれか}}{\mathsf{最高次数の係数の約数のどれか}}}\)で絞り込みができる!
なんでこの方法で絞り込みができるか詳しく知りたい人は「有理数解が見つけにくい3次方程式の解法」をチェック!
よって、因数定理より 左辺は\(\small (x-5)\)を因数に持つので
\begin{split}
&\small x^3-2x^2-17x+10=0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (x-5)(x^2+3x-2)=0\\
\small ∴ \space &\small x=5, \frac{-3\pm \sqrt{17}}{2}\\
\end{split}
これらの解の中で③を満たす解は \(\small x=5\)…【答】.
【パターン③】置き換えを利用した対数方程式(難易度:★☆☆)
次の方程式を解け。
(4)\(\small (\log_{5}x)^2+2\log_5 x =3\)
(5)\(\small \log_2 x-3\log_x 2=6\)
・2次方程式で求めた解が隠れた条件(真数条件や底の条件)を満たしているかの確認も忘れずに!
真数条件 :(真数)\(\small >0\)
底の条件 :(底)\(\small >0\) かつ (底)\(\small \neq 1\)
・解き方は、【講義2】[解き方②]対数を文字で置換する解法を参照。
\(\small (\log_5 x)^2\)が含まれていることから、\(\small t = \log_5 x\)…①とおく。
\(\small t\)の2次方程式を解く前に、\(\small x\)が満たすべき条件について確認しておく。本問では\(\small \log_5 x\)のように真数部分に\(\small x\)が含まれていることから、真数条件\(\small x >0\)…②を満たす。
問題の方程式を\(\small t\)を用いて表すと
\begin{split}
&\small t^2+2t = 3\\
\small \Leftrightarrow \space &\small t^2+2t-3=0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (t-1)(t+3)=0\\
\small ∴ \space &\small t= -3, \space 1\\
\end{split}
\(\small \log \)の定義として\(\small \log_a x =b \)は\(\small x=a^b\)となるので、①より、
\begin{split}
&\small t=-3\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_5 x=-3\\
\small ∴ \space &\small x= 5^{-3}=\frac{1}{125}\\
&\small t=1\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_5 x=1\\
\small ∴ \space &\small x= 5^{1}=5\\
\end{split}
これらの解はいずれも②を満たす(解の吟味を忘れない)。よって、\(\small \displaystyle x=\frac{1}{125}, \space 5\)…【答】.
底が満たすべき条件から、\(\small x \neq 1\)かつ\(\small x >0\)、真数条件から\(\small x>0\)を満たす。まとめると、\(\small x \neq 1, x>0\) …①.
今回の対数方程式は、底に\(\small x\)が含まれているため、底の変換公式を用いて
\begin{split}
&\small \log_x 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 x}=\frac{1}{\log_2 x}\\
\end{split}
のように底を\(\small \log_2\)に統一すると
\begin{split}
&\small \log_2 x-3\log_x 2=6\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \log_2 x-3\frac{1}{\log_2 x}=6\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (\log_2 x)^2 -6\log_2 x-3=0\\
\end{split}
\(\small t=\log_2 x\)とおくと、上式は
\begin{split}
&\small t^2 -6t-3=0\\
\small ∴ \space &\small t=3 \pm 2\sqrt{3}\\
\end{split}
ゆえに
\begin{split}
&\small \log_2 x =3 \pm 2\sqrt{3}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small x=2^{3 \pm 2\sqrt{3}}\\
\end{split}
上記の解は2つとも①の条件を満たすことから、方程式の解は \(\small x=2^{3 -2\sqrt{3}}\), \(\small 2^{3 + 2\sqrt{3}}\)…【答】.
【パターン④】種々の方程式を利用した対数方程式(難易度:★★★)
(1)次の連立方程式を解け。
\begin{cases}
\small \displaystyle \log_y x +\log_x y=\frac{5}{2}\\
\small \displaystyle \log_2 x +\log_2 y=\log_2 27\\
\end{cases}
(2)\(\small 8^{x\log_2 x}=x\sqrt{x}\)を解け。
・(1)は底の変換公式を用いることで\(\small \log_2 x\)と\(\small \log_2 y\)に関する連立方程式に帰着できる。
・(2)は指数部分を消去するために両辺の対数をとることで2変数を含む1次方程式に帰着できる。
真数に\(\small x,y\)が含まれることから真数条件より、\(\small x>0, \space y>0\)…①を満たす。また、底にも\(\small x,y\)が含まれているので、底の条件より \(\small x \neq 1, x >0\)かつ\(\small y \neq 1, y>0\)…②を満たす。
1行目の式について\(\small \log_2\)が底になるように底の変換公式で変換すると、
\begin{split}
&\small \displaystyle \log_y x +\log_x y=\frac{5}{2}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle \frac{\log_2 x}{\log_2 y}+\frac{\log_2 y}{\log_2 x}=\frac{5}{2}\\
\small \Leftrightarrow \space &\small \displaystyle (\log_2 x)^2+(\log_2 y)^2=\frac{5}{2}\log_2 x \cdot \log_2 y\\
\end{split}
ここで、式を分かりやすくするために\(\small X = \log_2 x\)、\(\small Y = \log_2y\)とおくと問題の連立方程式は
\begin{cases}
\small \displaystyle X^2+Y^2=\frac{5}{2}XY\\
\small \displaystyle X +Y=\log_2 27
\end{cases}
あとは上式の\(\small X,Y\)を求めていけばよいのだが、上式を見ると、\(\small X^2+Y^2=(X+Y)^2-2XY\)の関係式を用いることで、\(\small X,Y\)の和と積だけの形に式変形できるので
\begin{split}
&\small \displaystyle (X+Y)^2-2XY=\frac{5}{2}XY\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (\log_2 27)^2= \frac{9}{2}XY\\
\small \Leftrightarrow \space &\small XY = \frac{2}{9}(\log_2 27)^2\\
\small \Leftrightarrow \space &\small XY = \frac{2}{9}(3\log_2 3)^2\\
\small \Leftrightarrow \space &\small XY = 2(\log_2 3)^2\
\end{split}
となるので、
\begin{cases}
\small \displaystyle XY=2(\log_2 3)^2\\
\small \displaystyle X +Y=3\log_2 3
\end{cases}
のように\(\small X,Y\)の和(\(\small X+Y\))と積(\(\small XY\))の形で表現できる [*1]。
*1:【補足】基本対称式
\begin{cases}
\small \displaystyle X^2+Y^2=\frac{5}{2}XY\\
\small \displaystyle X +Y=\log_2 27
\end{cases}
の連立方程式は \(\small X\)と\(\small Y\)を入れ替えても式の形が変わらない(このような式を対称式というんでしたね)。対称式は必ず\(\small X+Y\)と\(\small XY\)を用いて表すことができるので、このことを知っていると上記のような式変形が自然とできるだろう。
\(\small X,Y\)の和と積の値が求まったのであとは、2次方程式の解と係数の関係から、\(\small X,Y\)は
$$\small t^2-3(\log_2 3) t +2(\log_2 3)^2 =0 \quad [*2]$$
という2次方程式を満たす(方程式の変数は\(\small t\)ではなくてもOK)。
*2:【補足】解と係数の関係と2次方程式
2次方程式 \(\small x^2 + ax +b = 0\)の2つの解を\(\small \alpha\)、\(\small \beta\)とするとき、解と係数の関係から\(\small \alpha\)、\(\small \beta\)は
\begin{cases}
\small \alpha +\beta =-a\\
\small \alpha\beta =b\\
\end{cases}
を満たす。
この関係を用いると、今回の2次方程式の2解\(\small X,Y\)が満たす2次方程式は
\begin{split}
&\small t^2-(X+Y)t +XY =0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small t^2-3(\log_2 3) t +2(\log_2 3)^2 =0\\
\end{split}
であることが分かる。
よって、2次方程式を解くと
\begin{split}
&\small t^2-3(\log_2 3) t +2(\log_2 3)^2 =0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (t-(\log_2 3))(t-2(\log_2 3))=0 \quad [*3]\\
\small ∴ \space &\small t= \log_2 3, \space 2\log_2 3\\
\end{split}
のように2解が求まる。
*3:【補足】2次方程式の因数分解
\(\small \log_23\)の形が含まれることで因数分解がややこしく感じるが、\(\small z=\log_23\)と文字でおいてあげれば
\begin{split}
&\small t^2-3(\log_2 3) t +2(\log_2 3)^2 =0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small t^2-3z t +2z^2 =0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (t-z)(t-2z)=0\\
\end{split}
のように因数分解ができることが分かる。
これらの解が\(\small X,Y\)であることから(もともと\(\small X,Y\)が満たす2次方程式が[*2]の式だったので)組合せを考慮することで、
\begin{split}
&\small (X,Y)= (\log_2 3, 2\log_2 3)、(2\log_2 3, \log_2 3)\\
\end{split}
\(\small X=\log_2 x\),\(\small Y=\log_2 y\)とおいていたので、
\begin{split}
&\small (\log_2 x,\log_2 y)= (\log_2 3, 2\log_2 3)、(2\log_2 3, \log_2 3)\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (\log_2 x,\log_2 y)= (\log_2 3, \log_2 3^2)、(\log_2 3^2, \log_2 3)\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (\log_2 \color{#ef5350}x,\log_2 \color{#5c6bc0}y)= (\log_2 \color{#ef5350}3, \log_2 \color{#5c6bc0}9)、(\log_2 \color{#ef5350}9, \log_2 \color{#5c6bc0}3)\\
\end{split}
上記はすべての底が\(\small \log_2\)で統一されているので対数の中身を比較することで
\begin{split}
&\small \color{red}{(x,y)= (3,9)、(9,3) \quad \cdots 【答】}\\
\end{split}
これらの解は①、②の条件をともに満たす。
\(\small \log_2 x\)があるので真数条件より、\(\small x>0\)…①。
指数部分に\(\small x\)が含まれているので両辺の対数をとることで対数方程式に帰着させる。
両辺にとる対数の底は指数部分に\(\small \log_2 x\)があるので、同じく底が2の対数(\(\small \log_2\))をとることで、底を統一するのがよいだろう。
すると問題の式は
\begin{split}
&\small \log_2 8^{x\log_2 x}=\log_2 (x\sqrt{x})\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (x\log_2 x) \cdot \log_2 8 = \log_2 x^{\frac{3}{2}} \\
\small \quad \space &\small ※左辺は\log_2 8^k =k\log_2 8を利用\\
\small \Leftrightarrow \space &\small 3x\log_2 x= \frac{3}{2}\log_2 x\\
\small \Leftrightarrow \space &\small 2x\log_2 x= \log_2 x\\
\small \Leftrightarrow \space &\small 2x\log_2 x-\log_2 x=0\\
\small \Leftrightarrow \space &\small (\log_2 x)(2x-1)=0\\
\end{split}
上記の方程式は『\(\small AB=0\)』ならば『\(\small A=0\)または\(\small B=0\)』であることを用いると
\begin{split}
&\small \log_2 x =0 \space または \space 2x-1=0\\
\end{split}
となるので、
\begin{split}
&\small \log_2 x =0 \space \Leftrightarrow \space x =2^0=1 \space \cdots ②、\\
&\small 2x-1 =0 \space \Leftrightarrow \space x =\frac{1}{2} \space \cdots ③\\
\end{split}
2解②、③はいずれも①の条件を満たすので、\(\small \displaystyle x =1, \space \frac{1}{2}\)…【答】.
本記事のまとめ
今回は対数方程式の典型問題の解き方についてパターン別に解説していきました。対数の中身の比較や文字の置き換えなどを用いることで、2次方程式や連立方程式などに帰着させて解く流れはそれほど難しくないと思いますが、解いた方程式の解が隠れた条件である真数条件や底の条件を満たしているかの解の吟味を忘れないように注意したいですね。
最後に本記事のポイントをおさらいして終わりにしましょう。
☆重要ポイント☆
[解き方①] 底を揃えて中身比較
・STEP1:真数条件、底の条件を確認する
・STEP2:両辺の底を揃える
・STEP3:対数の中身をイコールにして方程式を解く
・STEP4:求めた解がSTEP1の条件を満たすか確認する(解の吟味)
[解き方②] 対数を文字で置換する
・STEP1:真数条件、底の条件を確認する
・STEP2:logを丸ごと文字で置換する
・STEP3:置き換えた文字が満たす方程式を解く
・STEP4:求めた解がSTEP1の条件を満たすか確認する(解の吟味)
今回は以上です。お疲れさまでした!
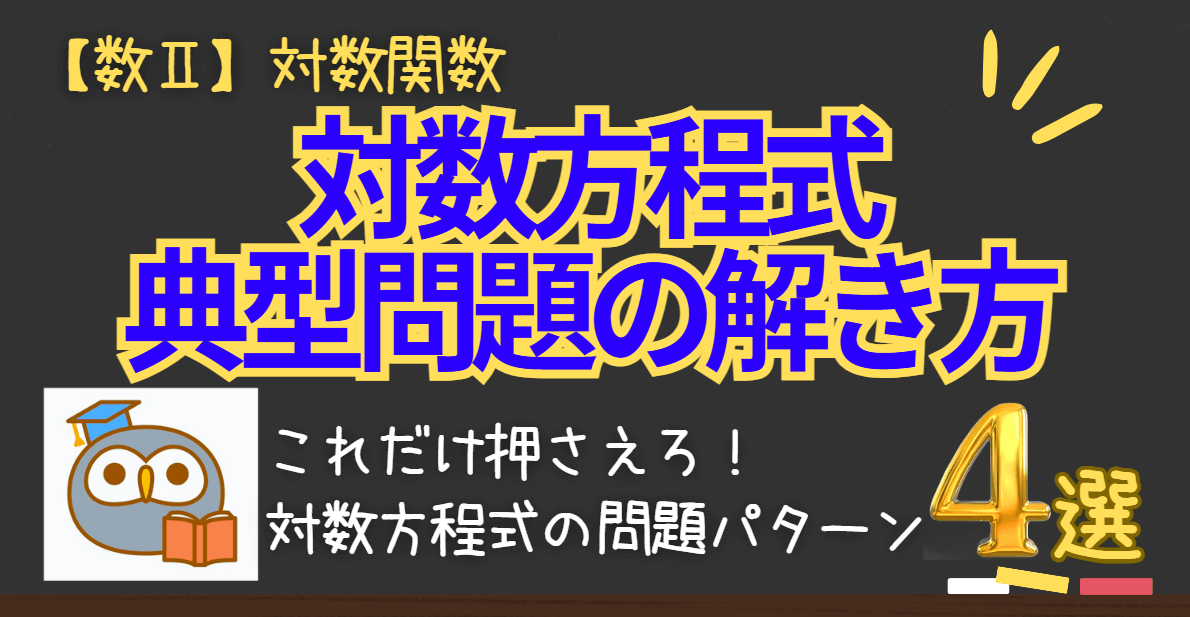
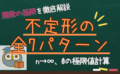
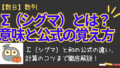
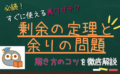


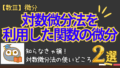
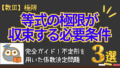
コメント